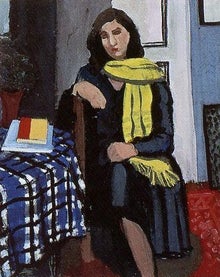岩城けいの「さようなら、オレンジ」(筑摩書房:2013年8月30日初版第1刷発行、2014年2月5日初版第5刷発行)を読みました。全体で166ページのこの作品は、岩代けいのデビュー作です。単行本の巻末に書かれている略歴によると、大阪生まれ、大学卒業後、単身渡豪。社内業務翻訳業経験ののち、結婚。在豪20年。本作で第29回太宰治賞を受賞。KSイワキより改名、とあります。そしてこの作品は第8回大江健三郎賞を受賞しました。大江は「私は『さようなら、オレンジ』の瀟洒なフランス装の本がパリで平積みされた光景を想像します」と述べています。
太宰治賞の選考過程が、以下のように載っています。
2013年5月8日、第29回太宰治賞の最終選考が、加藤典洋、荒川洋治・小川洋子・三浦しをんの四氏によっておこなわれ、満場一致にて「さようなら、オレンジ」は選出されました。選考委員全員が「この作品しかない!」という思い出決定された史上初の受賞作です。
本の帯の裏側には、以下のようにありました。
サリマの物語に寄り添うのは、はるかに時間をさかのぼり、誕生したばかりの言葉の原子に耳を澄ませるのに等しい。――小川洋子
まるで親しい友だちに対するように、読みながら応援したりハラハラしたり悲しんだり噴ったりした。――三浦しをん
また、第150回芥川賞候補作品の選考過程が、以下のように載っていました。
岩城さんの作品も、推す委員は『言語をいかに獲得していくか』ということの切実さと、逆に獲得していくことで失われるものがきちんと描けていて、感動があった。それに物語としても面白い、と。反対する選考委員はそれらの意見を認めつつ、アフリカ人のサリマ(登場人物の一人)をもっと深く描かなければ、物語として説得力を持たせることができないのではないかと指摘しました。
第150回芥川賞選評、川上弘美の談話(産経新聞:2014年1月20日 )
「さようなら、オレンジ」は、シャワーを浴びるサリマの様子を描いた文章で始まります。
サリマの仕事は夜が明けきらないうちから始まり、昼近くに帰宅した。家につくと洋服をむしり取って裸になり、すぐにシャワーを浴びた。この習慣は仕事を始めてからついてしまったもので、昼のさなかからたっぷりとお湯をつかってからだを洗うなんて贅沢を覚えた自分に腹を立てた。/シャワーの中で彼女はよく泣いた。
次の段落からは、サリマは自分が置かれた状況にしっかりと適応していきます。
仕事に就いてひと月たつと、サリマは泣くのをやめた。相変わらず生肉や魚の臭いがからだに染みついている気がして仕事から帰るとまっさきに」シャワーを浴びたが、もう泣くことはなかった。・・・それを横目で見やりながら、夫は出ていった。やっとの思いでここにともに逃れてきたというのに、夫はいともあっさり妻と子供を捨ててしまった。ついて来いとも待っていてくれとも言い残さなかった。
一方、恩師である「ジョーンズ先生」宛の「S」からの手紙は、次のようです。
いかがお過ごしでいらっしゃいますか。まさか、先生からお電話を頂けるなんて夢にも思いませんでした。それに先生の第一声が、「書いてるの?」。涙が出そうになりました。気に掛けてくださっていたこと、本当に嬉しかった。/早いもので、こちらに来てから半年が経ちました。住み慣れた都会からの移動は決して気乗りがしませんでしたが、夫の仕事とあっては仕方がありませんでした。
「さようなら、オレンジ」は、オーストラリアの田舎町に暮らす2人の女性を主人公とし、2人の視点が交互に出てくる形式で書かれています。一人は生死の危険をおかして脱出したアフリカ難民のサリマ、もう一人は高等教育を受けた日本人女性の「私」、サリマは「ハリネズミ」と呼んでいますが・・・。夫に逃げられたサリマは、精肉作業場で働きながら、なんとか二人の息子を育てています。母語の読み書きすらままならない彼女は、職業訓練学校で英語を学び始めています。
そこで出会ったのが、研究者の夫について渡豪した、生後4ヶ月の娘がいる日本人女性、彼女は母語ではない英語で小説を書こうとしています。サリマから見れば、彼女は主婦のかたわら勉強という恵まれた境遇に見えます。しかし彼女はすでにこの地に数年住みつつ、なお順応できない苦しみを抱いています。
この作品の1/3のところで、ある痛ましい出来事をきっかけに、二人は急速に接近します。「私」の幼い娘が突然亡くなります。「私」に起こった娘の死という悲劇をきっかけに、サリマと「私」の間の関係が深まります。サリマは「お国のことを子供たちにお話ししていただけたら」と、下の息子の担任教師に声をかけられます。「私の故郷」というテーマでシナリオをつくり、写真などを織り交ぜてプレゼンテーションを行うというものです。教師は題名の「私の故郷」をフェルトペンで消し、「サリマ」と直しましたが・・・。
サリマは作文を読み上げ始めます。
砂のうえで私は育った。お父さん、お母さん、弟たち。はたけの作物はぴかぴかしていて、もう食べられる。そんなゆめを見ていたと思うことにした。オレンジ色のおひさまがいつもうかんでいる、ゆめ。
サリマが読み終えると子供たちはしずまりかえったままでした。教師はあまりにも個人的すぎて役に立つ内容ではないという意見でしたが、子供たちはつぎつぎに質問の手を上げます。サリマは長い放浪の旅をおえてようやく自分の居場所に落ち着いたような心持ちがしました。
その手伝いをしたのが、時間と労力を惜しまないハリネズミである「私」でした。幼い娘を失った後、いったんはサリマと同じ職場で働き始めます。英語のクラスでおどおどして天気予報ばかり読まされていたナキチもいました。職場では堂々たるチーフで、ナイフの持ち方から肉魚の裁きかたなどすべてを教わりました。彼女の母語は部族語ですが国のごたごたで勉強できずに、ほぼ文盲の状態です。サリマは「あなたはダイガクへ行くべきだわ」と「私」に言います。悲劇を乗り越えた「私」に、新しい命が宿ります。
「夫婦の友人たちへの告知と、悲劇を乗り越えての新しい出産の報告とは、小説の二つの文体のなかに英文で二葉挿入されて、視覚的な効果もあげます」と、大江健三郎は述べています。続けて、この「私」に起こった悲劇をきっかけにサリマたちと「私」の間に新しく深まった関係が、小説の展開をみちびきます、と。
永住を決意したことを節目として夫と一緒に娘の灰を海に撒く「私」、水平線のかなたに夕日が沈み掛かっています。壺の蓋をあけ、手のひらに載せた灰はほんの一瞬だけあたりを煙らせて夕日の色に染まり、風に乗ってどこかへ消えました。さようなら、私の愛しい子、と最後に心の中で叫びましたが、これからはあの夕日のなかにあの子がいるような気がして、さようならを言いながら、わたしが見ている夢のようにうつくしいオレンジ色はたったいま特別になったのだと思うと、それは心慰められることでした。
夫の仕事が契約から正規採用になったのを機に、夫の勤務地にほど近い築30年の小さな家を購入します。大学の履修届に行ってみると、てっきり除籍になっていると思っていたが、「私」学の生番号が学籍簿に残っていました。
フラットへ戻る道を歩きながら、私はナチキのことを思います。フラットの前まで来て、階上へ続く鉄の階段を駆け上がったとき、もうひとりの私が私に耳打ちする声が聞こえました。私の大切な友達のことを書こう、書かなければならない。ドアノブにキーを差し込み、ロックが外れる音を聞いたとき、ヒロインの名は「サリマ」だ、と思いました。ナキチは戦火でお母さんと生き別れになっています。だから、もし自分に娘が生まれていたら、お母さんの名をもらってこの名をつけるつもりでいたそうです。
先生。いまから私がここに書くことは、英語という私にとって第二言語から学んだこと、英語で書くことによって、徹底的に壊し、作り直し、新たに躾なおした思考と行為を決して無駄にはしない、つまり先生への感謝の言葉だと思って受け取ってください。私が「先生」と呼びかけるのは、ジョーンズ先生だけなのですから。実は、あのあと部屋に入るなり、いてもたってもおられず数行の出だしを書いてみました。
ところが、英語にならないのです。日本語にしかならないのです。先生、私は自分の言葉で書くのがこわい。心理的に正直に書くことが恐ろしくてたまらないのです。私はいままで、そういった人の心の奥底にある感情の沼を恐れるあまり、真摯に受け止めることができず、表面だけを器用にとりつくろうことしかできない不器用な言葉、第二言語である英語を隠れ蓑にして綴ってきました。それが今回はできそうにありません。してはいけない気がするのです。
そしてこの物語は、「S」からの、ジョーンズ先生への感謝の手紙で終わります。
大江健三郎は、「晩年様式集(イン・レイト・スタイル)」が文庫本になるとして、自分が80歳を超えていることを考えて、細部の検討をこの間まで続けてきたという。「晩年様式集」を読み直しながら、晩年をきわまっての生き方を考えもしたが、大江健三郎賞を今回で終えることに思い至ったのは、これからなお本を読み、なんらかの仕事をするにしても、それは自分が新しい(若い)作家たちと同時代の作家としてではないはず、と覚悟せざるをえなかったからです、と述べています。そして岩波文庫から「短篇自選集」を出す準備をしていて、最初の短篇「奇妙な仕事」に新鮮な印象を受けたことを告白します。そして「奇妙な仕事」の末尾を57年ぶりに書き写して、私たちに提示します。
歴代大江健三郎賞 受賞作・受賞者
![ooe2]() 「群像 2014.5」
「群像 2014.5」
2014年5月1日発行
発行所:株式会社講談社
「第8回大江健三郎賞発表」
関連記事:
大江健三郎賞に岩城けいの「さよなら、オレンジ」が!
本谷有希子の「自分を好きになる方法」を読んだ!
本谷有希子の「嵐をピクニック」を読んだ!
本谷有希子「嵐のピクニック」軽さへの冒険、新境地!
大江健三郎賞に本谷さん!
「第7回大江健三郎賞・公開対談」を聞く!
第6回大江健三郎賞発表、綿矢りさ「かわいそうだね?」
綿矢りさの「かわいそうだね?」を読んだ!
「第5回大江健三郎賞、大江健三郎と受賞者・星野智幸の公開対談」を聞く!
第5回大江賞に星野智幸さん 受賞作は「俺俺」!
星野智幸の「俺俺」を読んだ!
「第4回大江健三郎賞 大江健三郎と中村文則の公開対談」を聞く!
中村文則の「掏摸」を読んだ!
大江健三郎賞に中村文則の「掏摸」が!
芥川賞受賞作、中村文則の「土の中の子供」を読む!
「第3回大江健三郎賞 大江健三郎と安藤礼二の公開対談」を聞く!
第3回大江健三郎賞選評と、安藤礼二の「光の曼陀羅」を読んだ!
安藤礼二の「光の曼陀羅 日本文学論」が大江健三郎賞に!
「第2回大江健三郎賞公開対談 大江健三郎×岡田利規」を聞く!
岡田利規の「わたしたちに許された特別な時間の終わり」を読んだ!
第2回大江健三郎賞に岡田利規さん!
長嶋有の「夕子ちゃんの近道」を読んだ!
第1回大江健三郎賞に長嶋有さんの「夕子ちゃんの近道」
講談社が「大江健三郎賞」創設 選考は大江氏1人