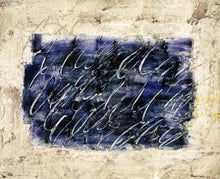「日本美術の祭典」
2014年、上野の新春は「日本美術の祭典」で幕を開けます。東京国立博物館と東京都美術館のコラボレーションにより、両館で開催される3つの展覧会を結ぶ特別なプロジェクトが実現しました。時代を超えて輝きを放つ絵画や工芸の名品に触れることで、さまざまな日本の美を再発見していただこうという新しい試みです。当館では2つの特別展を同時開催します。「クリーブランド美術館展―名画でたどる日本の美」は、全米屈指といわれる同館の日本美術コレクションから、仏画や肖像画、花鳥画、山水画などを選りすぐって公開するものです。日本伝統工芸展60回記念「人間国宝展―生み出された美、伝えゆくわざ―」では、歴代の人間国宝や先人が残した古典の名作を展観し、日本が誇る工芸の精華を紹介します。一方、東京都美術館で開かれる日本美術院再興100年特別展「世紀の日本画」には、近代日本画の巨匠たちの代表作が勢揃いします。 日本美術の粋が上野に集結するまたとないこの機会、素晴らしき三重奏をお楽しみください。
東京国立博物館で「クリーブランド美術館展 名画でたどる日本の美」を観てきました(この展覧会は終了しました)。
クリーブランドという街がアメリカのどこにあるのかは知らないのですが、「クリーブランド美術館展」と聞いて、たしか過去に展覧会があったように思い調べてみたら、やはりありました。六本木の森アーツセンターギャラリーで2006年9月9日(土)~11月26日(日)、「クリーブランド美術館展」が開催されていました。僕は残念ながら、観に行っていません。
「女性美の肖像 モネ、ルノワール、モディリアーニ、ピカソ ~ この秋、あなたはどんな女性美の肖像と出遭いますか。 ~」という長い副題がついていました。2011年の完成を目標に美術館の増改築工事が行われていて、その期間、作品の貸し出しが可能になりました。増改築工事の設計は、東京国際フォーラムの設計者である建築家ラファエル・ヴィニョーリでした。どんな素晴らしい美術館になったか、興味津々です。
前回はモネ、ルノワール、ドガ、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャンなどの印象派・後期印象派の作品から、近代彫刻の先駆者ロダン、そして、マティス、ピカソ、マグリットなどの20世紀美術まで、西洋近代美術の流れを概観するという展覧会でしたが、今回は一転、「名画でたどる日本の美」です。
今回の展覧会の見どころは、まず全米屈指の規模と質を誇るクリーブランド美術館の日本美術コレクションが里帰り、ということにあります。そこには、雪村、始興、蘆舟、蕭白に暁斎。人気の絵師が勢ぞろいしました。作品は平安から明治まで、日本絵画の流れと魅力を約50件の名品でたどっています。一部、「近代西洋の人と自然」ということで、ピカソ、モネ、ルソーなど、西洋絵画の名品も数点、展示してありました。
展覧会の構成は、以下の通りです。
第一章 神・仏・人
第二章 花鳥風月
第三章 山水
終章 物語世界
第一章 神・仏・人
日本の絵画は中国からその主題と表現を学びました。神仏の姿や人のかたちの表現もまた、その影響のもとにありました。それらは、日本の信仰感情や風土にあわせ、時代ごとに変遷していきます。平安末から明治までに描かれた仏画や物語絵巻、肖像画などの優品を通して、日本絵画がどのように人体をとらえ、表現したのかをご覧いただきます。
第二章 花鳥風月
自然は人々に豊かな恵みと潤いをもたらすものとして憧れの対象であると同時に、天災を引き起こす怖れの対象でもありました。日本の絵画では生命を育む自然や動物は、人々の暮らしと密接なものとして表されています。さまざまな表現の花鳥画や走獣画(動物画)を通して、日本における自然観が、どのように絵画にあらわされたのかを明らかにします。
第三章 山水
日本の風景画―山水画も、中国絵画から多くを学びました。水墨画という、風景を目でみたままに描くことができる技法を手に入れたのです。しかし、その後日本では、独自の表現の展開がみられるようになります。室町から江戸時代に描かれた山水画をご覧いただくことで、日本における「理想の世界」がどのように表現されたのかを探ります。
終章 物語世界
日本に伝わる物語は、人と自然が対立するものでなく、いわば渾然一体のものとして語られてきました。そこでは、生き物や植物をとりあげることで、登場人物の心情まで表されました。近世に広く広まった『伊勢物語』にかかわる絵画を展示し、人と自然がどのような関わりをもって表されたのかをご覧いただきます。
特別展示 近代西洋の人と自然
「クリーブランド美術館展 名画でたどる日本の美」
過去の関連記事:
東京国立博物館で「人間国宝展」を観た!
東京国立博物館東洋館で「上海博物館 中国絵画の至宝」(前期)を観た!
東京国立博物館で「飛騨の円空―千光寺とその周辺の足跡―」を観た!
東京国立博物館平成館で「中国 王朝の至宝」展を観た!
東京国立博物館平成館で「ボストン美術館 日本美術の至宝」(曾我簫白編)を観た!
東京国立博物館平成館で「ボストン美術館 日本美術の至宝」を観た!
東京国立博物館平成館で「空海と密教美術展」を観た!
東京国立博物館平成館で「特別展 写楽」を観た!
東京国立博物館平成館で「長谷川等泊」展を観た!
東京国立博物館平成館で「阿修羅展」を観た!
東京国立博物館平成館で「妙心寺」展を観た!
東京国立博物館・平成館で「対決-巨匠たちの日本美術」展を観る!