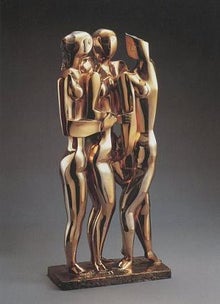山田洋次監督の「東京家族」を観ました。1月26日(日)夜9時からテレビで放映されたものを、録画しておいたのですが、なかなか観る時間がとれなくて、やっと今日、観ることができました。なにしろテレビの録画時間は2時間54分(公式には146分)と長いので、観るのを躊躇したこともあります。実は「東京家族」の次回作、山田洋次監督の「小さいおうち」、現在公開中なので観に行きたいのですが、なかなか観に行く時間がとれません。その前に是非とも観ておくべきということで、「東京家族」を観たというわけです。
小津安二郎監督の「東京物語」は、ビデオを借りて観た記憶があります。NHKBSプレミアムの「山田洋次監督が選んだ日本の名作100本」にも入っていました。「東京物語」は、年老いた両親の東京旅行を通じて、家族の絆、夫婦と子供、老いと死、人間の一生、それらを冷徹な視線で描いた作品、とされています。公開されたのが1953年、僕はまだ子供でした。笠智衆と原節子のことはよく覚えています。笠智衆が東京で落ち着きを感じることが出来た場所が、原節子の住む「公営住宅」と、銀座松屋屋上の「展望塔」の2箇所でした。2012年、世界の「映画監督が選ぶベスト映画」の1位に選ばれたのが、小津安二郎監督の「東京物語」でした。
山田洋次監督生活50周年の節目でもある「東京家族」は、小津安二郎監督の「東京物語」をモチーフに製作されたことは、よく知られています。クランクイン前に東日本大震災が起こり、撮影は延期され、それらの記憶も織り込んで製作に取り組み、2012年に公開されました。たとえば「東京物語」で原節子演じる戦死した次男の妻の紀子の役割は、妻夫木聡演じる次男・昌次と蒼井優演じるその恋人になっていますが、東日本大震災のボランティア活動で二人は知り合った、ということになっています。
映画はキャストが命。口数が少なく頑固だが一本筋の通った父、周吉を演じるのは橋爪功。おっとりしていて茶目っけのある母とみこには吉行和子。町医者で長男・幸一には西村雅彦、妻の文子に夏川結衣、美容院経営の長女・滋子に中嶋朋子、その夫の庫造に林家正蔵が扮しています。舞台美術を仕事にしている次男の昌次には妻夫木聡、その恋人で書店員の紀子には蒼井優。この二人が主役と言ってもいいほどの役割です。他に修吉の友人・小林稔侍や飲み屋の女将・風吹ジュンらも、いい演技をしています。
子供たちの様々な事情で横浜のホテルに宿泊することになった周吉ととみこ。ただ外を眺めるだけで、やることのない二人。修吉はネオンに輝く観覧車を見て、結婚する前に二人で観た映画「第三の男」を懐かしむ。ホテルの部屋から観る横浜の夜景はどこか寂しい。二人には、寝苦しい夜が続きます。
お客の要求で書店員の蒼井優が取り出した絵本が、バージニア・リー・バートンの「ちいさいおうち」(石井桃子訳、岩波書店:1965年12月発行)というのも、次回作をさりげなく告知していて面白い。
以下、とりあえず「シネマトゥデイ」より引用しておきます。
チェック:『男はつらいよ』シリーズや『たそがれ清兵衛』『おとうと』などで知られる、山田洋次の監督81作目となるファミリー・ドラマ。瀬戸内の小島から上京し、自分の子どもたちと久々の対面を果たした老夫婦の姿を通して、現代日本における家族の在り方や絆などを見つめていく。『奇跡』の橋爪功、『人生、いろどり』の吉行和子、「古畑任三郎」シリーズの西村雅彦、『悪人』の妻夫木聡などの実力派が集結し、いつの間にか生じた隙間を埋めようとする家族を熱演する。随所にちりばめられた、山田監督による巨匠・小津安二郎の『東京物語』へのオマージュも見逃せない。
ストーリー:瀬戸内海の小さな島で生活している夫婦、平山周吉(橋爪功)ととみこ(吉行和子)。東京にやって来た彼らは、個人病院を開く長男・幸一(西村雅彦)、美容院を営む長女・滋子(中嶋朋子)、舞台美術の仕事に携わる次男・昌次(妻夫木聡)との再会を果たす。しかし、仕事を抱えて忙しい日々を送る彼らは両親の面倒を見られず、二人をホテルに宿泊させようとする。そんな状況に寂しさを覚えた周吉は、やめていた酒を飲んで騒動を起こしてしまう。一方のとみこは、何かと心配していた昌次の住まいを訪ね、そこで恋人の間宮紀子(蒼井優)を紹介される。
「東京家族」公式サイト