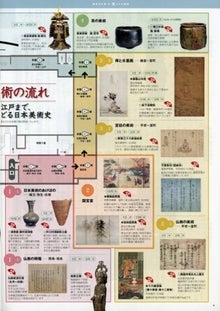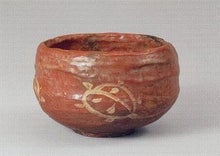僕が篠原有司男を初めて知ったのは、1974年1月から2月にかけて東京国立近代美術館で開催された「アメリカの日本作家」展です。なぜかその時の図録があるんですが、それを見ると今ではそうそうたる人が出品しています。そこに篠原は「モーターサイクル・ママ」という、やはり段ボールで作ったオートバイを出品しているんですね。この作品にはショックを受けました。なにしろ圧倒的な量感、疾走感なんですから。当時はあまり色は使ってはいませんでしたが。その時のプロフィールを見ると「57年東京芸大卒業後、60年グループネオ・ダダを結成、モヒカン刈りでのボクシング・ペインティングを始める。」とあります。そうでした、その頃の篠田はモヒカン刈りでしたよ。懐かしい。グループネオ・ダダとは、1960年、篠原有司男、荒川修作、赤瀬川原平など10人の作家が集まって「ネオ・ダダ・オルガナイザーズ」を結成したものです。既成の美術概念に反発して、当時様々なイベントを繰り広げました。篠原の最近のというか、今までの活動は、すべて1960年代の「たどり直し」とも言えるかも知れません。
「アメリカの日本作家」展の、僕のお目当ては池田満寿夫でした。池田は1934年生まれ、篠原は1932年生まれ、2歳違いです。一方は芸大受験失敗の版画家、一方は芸大卒のアバンギャルド“ネオ・ダダ”です。どちらも当時、NY在住でした。2005年1月に篠原有司男展を観たときに、上のように書きました。
篠原有司男新作展
「アメリカの日本作家」展の図録を探したら、本棚の奥にありました。その図録の間に挟まっていた幾つかのものを下に載せておきます。
・2005年1月17日朝日新聞の切り抜き「篠原展、練達の持続と娯楽」
・2001年7月12日朝日新聞「篠原有司男展」「大平實展」、「拡散する疾走感と急進的緊張」
・ギャラリー山口「篠原展」作品リスト
・2001年6月9日~7月22日府中市美術館公開制作
「篠原有司男 ピラニアと格闘する前衛アーティスト―作品展示、パフォーマンス、ワークショップ」チラシ
・徳島県立近代美術館 学芸員作品解説1991年5月29日徳島県立近代美術館 江川佳秀
2005年の朝日新聞の記事には、以下のようにあります。
「篠原有司男新作展」。ギュウちゃんの愛称で呼ばれる篠原は1932年生まれ。69年からニューヨークに住み、段ボールや廃品で作った「オートバイ彫刻」や、原色の交錯する動的な絵画で知られる。計4点。彫刻はやはりオートバイで「女と兎と蛙を従えたストロベリーアイスクリームをなめる髑髏バイク」(04年)という長い題。「テロリストアタック直後のニューヨーク」の副題を持つ、長さ3.7mの大作だ。
また2001年の朝日新聞の記事には、以下のようにあります。
この2月、ニューヨークの篠原有司男を訪ねた。雑然とした町工場のようなアトリエに、「ポケモン」の漫画本が30巻も並んでいた。その篠原の個展が今、東京で開かれている。新作5点と旧作1点。なるほど新作「ポケモン・モーターサイクル」(2000年)などの作品に、ポケモン研究の成果であるさまざまなキャラクターがモチーフとして取り込まれている。
ギャラリー山口「篠原展」作品リストを、項目だけ載せておきます。
「ガウディパークのポケモン」「雪舟対決」「南海」「八窓席」「ポケモン・モーターサイクル」「空海モーターサイクル」、の6点です。
さて、今回の渋谷・パルコミュージアムの展覧会。現代アーティスト篠原有司男、その妻であり芸術家である乃り子。二人の波乱に満ちた結婚生活を描いたドキュメンタリー映画「キューティー&ボクサー」の日本公開を記念した展覧会「篠原有司男・篠原乃り子二人展 愛の叫び東京篇」です。「アートに命を賭けた二人だからアートを観なければ始まらない!」と副題が付けられています。乃り子による「キューティー&ブリー」の大作絵巻絵画や、有司男の「ボクシング・ペインティング」最新作、「オートバイ彫刻」などの名作が展示されています。
夫・篠原有司男は通称ギュウちゃん。1932年東京に生まれる。1960年に芸術グループ「ネオダダ」を結成、版芸術のアクション・アートで注目を集める。日本で初めて“モヒカン刈り”にした反骨精神溢れる若者は「ひたむきなベラボウさ」で故・岡本太郎氏を驚愕させた。1969年に渡米、以来NY在住。「ボクシング・ペインティング」で知られる現代芸術家はアートの猛者。80歳をこえても“前衛の道”をひた走る。
そんな純粋さに魅せられたのが妻・篠原乃り子。1953年高岡市に生まれる。1972年、美術留学で渡米。有司男と恋に落ち、結婚。さっそく男児を授かる。芸術家の“大人の子供”の面倒を見ながら“母の道”を歩む乃り子。だが、ついに自分の表現を発見―それは自らの分身“キューティー”の波瀾万丈の絵物語だった。
そんな二人を美術史家として見つめてきたのが1988年よりNY在住の富井玲子。アメリカでもハチャメチャに展開していく有司男のエネルギーに圧倒され、寡黙にアートの可能性を探る乃り子に同じ女性として感銘をうけてきた。二人の晴れの舞台にゲスト・キュレーターとして協力する。
篠原有司男作品
篠原乃り子作品
「篠原有司男 ピラニアと格闘する前衛アーティスト
―作品展示、パフォーマンス、ワークショップ」
チラシ
過去の関連記事: