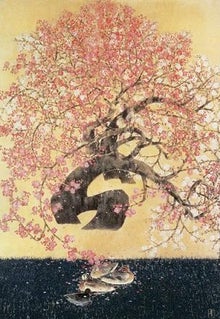「眺めのいい部屋」は、以前、見た記憶があるのですが、詳しいことは覚えていません。上の画像は、1990年夏にフィレンツェへ立ち寄った時のスライドをスキャンしたものです。フィレンツェにはその後、2004年冬にも行きました。フィレンツェの街と建築を観に行ったのでした。ミケランジェロ広場からアルノ河、フィレンツェ市街を見た画像、サンタ・マリア・デル・フィオーレのクーポラや、ヴェッキオ宮殿の塔が見えます。
「グランドツアー」は、イギリスの支配階級や貴族の子弟たちが、教育の最後の仕上げとして体験することになる、比較的長い期間のイタリア旅行のことで、17世紀の末に始まり18世紀後半においてピークに達したといわれる。(岡田温司著:「グランドツアー18世紀のイタリアへの旅」より)
1907年。イギリスの良家の令嬢ルーシー・ハニーチャーチ(ヘレナ・ボナム・カーター)は、年上の従姉シャーロット(マギー・スミス)に付き添われ、イタリアのフィレンツェを訪れます。女性が、しかも時代は20世紀初頭ですが、まさに「グランドツアー」そのものです。二人は、部屋が美しいアルノ河に面した側でないことにがっかりします。シャーロットが苦情を言いたてるのを聞いたエマソン(デンホルム・エリオット)は息子のジョージ(ジュリアン・サンズ)と共に泊っていた「眺めのいい部屋」と交換してもいいと申し出てくれました。このエマソン父子は、なかなか進歩的な考えの持ち主です。一度はためらったシャーロットでしたが、偶然に同宿していたハニーチャーチ家の教区のビーブ牧師(サイモン・カラウ)に説得され、申し出を受け入れました。
「眺めのいい部屋」に移って気をよくしたルーシーとシャーロット。ラヴィッシュ女史(ジュディ・デンチ)とシャーロットは、フィレンツェの街へと繰り出します。まず出てくるのがアヌンツィアータ広場、アヌンツィアータ教会とブルネッレスキの設計による捨て子養育院が広場を取り囲んでいます。この映画は、フィレンツェがあってこその映画です。フィレンツェに始まり、フィレンツェに終わります。ラヴィッシュ女史はルーシーに目を付けていて、「イタリアで変わりゆく若い英国の娘」として小説の登場人物にして書きたいと思っています。
翌朝一人で町を見物していたルーシーは、サンタ・クローチェ教会へ入って壁画などを見学していると、しつこいイタリア人ガイドに付きまとわれたりします。壁画や天井画の説明を聞いていると、部屋を譲ってくれたエマソンとバッタリ出会います。一緒に礼拝堂の壁画を見て回ります。映画の中ではかなり大きな教会に見えました。ここは見るべきものが盛りだくさんです。ジオットの壁画のあるバルディ礼拝堂が有名です。一度目は見逃したのですが、二度目で観ることができたのは、サンタ・クローチェ教会の正面右手にある中庭の奥にあるブルネッレスキのパッツィ家礼拝堂です。小さな建築ですが、ブルネッレスキの最高傑作です。
シニューリア広場の前のヴェッキオ宮殿、この塔はフィレンツェのどこからでも見ることのできるランドマークです。シニューリア広場のヴェッキオ宮殿に入る左側にミケランジェロのダヴィデ像があります(本物はアカデミア美術館に移されていますが)。その横にはウフィッツイ美術館があります。ジオット、マザッチオ、ブルネッレスキ、ドナテッロ、ボッティチェッリ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエッロ・・・の名が矢つぎ早に思い出されます。
その前で男同士の争いが起こり、一人が胸を刺されて目を剝いて死にかけています。それを見たルーシーが失神しそうになると、タイミングよく出てきたのがエマソンの息子・ジョージでした。シニューリア広場の横にロッジャと呼ばれる彫刻を展示してあるところがあります。ルーシーはジョージにロッジャに連れて行かれて介抱されます。ルーシーが落とした写真を撮ってきてくれるように頼むと、その間にジョージから逃げようと思いますが、二人はアルノ河を見ながら、いつの間にか引かれ合うようになります。ジョージは写真をアルノ河に投げ棄てます。二人の後にはヴェッキオ宮殿の塔が映っています。ある日ピクニックに出かけたルーシーは、同行したジョージと青い麦畑の中で情熱的なキスを交わします。二人の仲に気づいたシャーロットは、ルーシーをイギリスに連れ帰ってしまいます。
数ヵ月後、ルーシーは、高い教養の持ち主であるシシル・ヴァイス(ダニエル・デイ・ルイス)と婚約します。シシルは上流階級でしょうが、なんとも鼻持ちならないヤツです。そんな矢先、偶然にもロンドンの美術館でエマソン父子と会ったシシルは、ルーシーの家に近い貸家の世話をします。やがてルーシーはジョージと再会します。ルーシー家の人々とテニスに興じるジョージ。ルーシーの弟が気が利いていて、ピアノでおどけたりしてなかなかよろしい。傍でラヴィッシュ女史(ジュディ・デンチ)の書いた小説をキザっぽく読み上げるシシル。テニスの帰りがけ、再びジョージから熱いキスを受けたルーシーは、シシルとの婚約解消を決意します。音楽については詳しいことは分かりませんが、ルーシーの弾くピアノも、前半はベートーヴェン、後半はモーツアルトへと変化します。
秋、「眺めのいい部屋」に、ルーシーとジョージは再びフィレンツェにやって来ました。シャーロットにフィレンツェに到着したことを手紙で告げます。私たちが泊まった宿は少しも変わっていないと。シャーロットも若い頃はルーシーと同じ体験をしたのではないでしょうか。しかし今は夢破れて独身でいます。朝食の時に、前の若い女性が「眺めのない部屋なんて」と母親らしき人に言います。「おやめなさい。明日の朝、女将と話してみます」と答えます。「ひどすぎるわ。初めてのフィレンツェは眺めが大切よね」と娘が言います。それを見ていたルーシーとジョージは、「僕らはあります」と見つめ合います。
次の日、窓の外には、サンタ・マリア・デル・フィオーレのクーポラと、ヴェッキオ宮殿の塔が見えます。フィレンツェの美しい風景が広がるなかで、二人は熱いキスを交わすのでした。
以下、とりあえずシネマトゥデイより引用しておきます。
チェック:『ハワーズ・エンド』のジェームズ・アイヴォリーが、『モーリス』の原作で知られるE・M・フォスターの小説を映画化したドラマ。イギリス名家の令嬢が、フィレンツェへの旅とそこで出会った男性との恋を通し、内面的成長を遂げる姿を見つめる。ヒロインにふんするヘレナ・ボナム=カーターを筆頭に、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』のダニエル・デイ=ルイス、『007』シリーズのジュディ・デンチと、イギリスの実力派スターが結集。彼らの若き日の姿もさることながら、フィレンツェの美しい風景も見ものだ。
ストーリー:1907年。名家の娘ルーシー(ヘレナ・ボナム=カーター)は、従姉のシャーロット(マギー・スミス)と一緒にフィレンツェへ。現地に到着してすぐに、宿の部屋からの眺めが良くないとシャーロットが騒ぎ出して困惑するルーシーだが、それを耳にしたジョージ(ジュリアン・サンズ)が部屋の交換を申し出る。その後もフィレンツェの街で再会したルーシーとジョージは、互いを強く意識するように。しかし、その様子に気付いたシャーロットがルーシーを連れて帰国。数か月後、ルーシーはセシル(ダニエル・デイ=ルイス)という男性と婚約する。
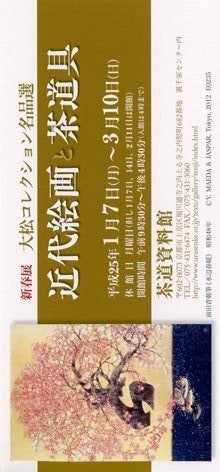 入場券
入場券 「一盌からピースフルネスを」
「一盌からピースフルネスを」  「京都・今出川通の美術館だより」
「京都・今出川通の美術館だより」