今日は京都!
今朝の京都駅です!
名古屋・京都 美術館めぐり
22日から4日間、金沢方面へ行く予定でしたが、何となく気が進まず、数日前に行き先を急遽変更、3日間の予定で名古屋と京都に行ってきました。とりあえず名古屋と京都に一泊ずつホテルを予約しただけで、あとは出たとこ勝負の小旅行でした。とはいえ、まずは愛知県美術館で「クリムト 黄金の騎士をめぐる物語」を観ること、細見美術館で「江戸絵画の至宝 琳派と若冲」を観ることが、名古屋・京都での目的でした。
名古屋へ行ったら、まずは昼は山本屋本店の「味噌煮込みうどん」、夜はあつた蓬莱軒の「ひつまぶし」を食べること。「味噌煮込みうどん」は名古屋の友人に連れて行ってもらい食べたことがありますが、「ひつまぶし」は初体験でした。そして近鉄の前のナナちゃんを見ること、ナナちゃんは愛・地球博のときに見ていましたが、再び見てきました。写真では何度も見ていましたが、日建設計がやった捻れた建築を実際に見ること。まあ、こんなささやかな目標は達成しました。もちろん愛知県美術館での「クリムト 黄金の騎士をめぐる物語」は、しっかりと観てきました。
京都の一日目は、細見美術館で「江戸絵画の至宝 琳派と若冲」を観ること、細見美術館へ行くのは初めてのこと、なんと前川さんの「京都会館」のすぐ近くにありました。小さいながらも地下までの吹き抜けを上手く使った美術館でした。残念ながら、外壁材がやや薄汚れてはいましたが。もちろん、「琳派と若冲」は、小品がほとんどでしたが素晴らしいものばかりでした。細見美術館については、2009年6月に日本橋高島屋で開催された「細見美術館開館10周年記念展 日本の美と出会う―琳派・若冲・数寄の心―」で僕は初めて知りました。以来、京都へ行ったらぜひ訪れて見たいと思うようになりました。去年、そごう美術館で京都 細見美術館展「都の遊び・王朝の美―美を愛でる、京を知る―」と「琳派・若冲と雅の世界」を観ました。
前川さんの「京都会館」、詳しいことは分かりませんが、どうも解体されるようです。
そうそう、京都で行ってみたい美術館と思っていたのが「清水三年坂美術館」、たまたま「鍛鉄の美―鐙(あぶみ)、鐔(つば)、自在金物」という展覧会をやっていました。僕は特に自在金物を観てみたくて、清水三年坂美術館へと行ってきました。自在金物はさすがに数は少なかったのですが、他に「蒔絵」や「七宝」など、素晴らしいものばかりでした。
さて京都の第二日目は、京都国立博物館で「特別展覧 国宝十二天像 密教法会の世界」を観てきました。同時開催として「成立800年記念 方丈記」がありました。国宝十二天像、いや、もう、第一室に展示されている「国宝十二天像」12幅をみただけで、ぐったりしてしまうほどでした。なにしろ国宝、重要文化財が目白押しですから、凄いのなんのって・・・。とはいえほとんど半分は分かりませんでしたが・・・。
京都国立博物館、切符売り場の辺りから、これは谷口建築だなと思いました。ちょうど「新館?」が工事中で、その設計は谷口吉生の名前が出ていました。実は金沢へ行こうと思ったのは、谷口さんが設計した「鈴木大拙館」を観に行きたかったからでした。以前、酒田の「土門拳記念館」へ行った時、雪が降っていたことがあるので、「鈴木大拙館」も、冬、雪が降っていてもいいかなと・・・。
他に京都では、偶然見つけたのですが、「茶道史料館」で「新春展 大松コレクション名品選 近代絵画と茶道具」、これが思っていた以上に素晴らしい展覧会でした。茶道具の他に、横山大観、前田青邨、川合玉堂、上村松園など、名だたる画家の日本画が展示されていました。また抹茶の接待もありました。そして次は近くにあった楽美術館で「楽歴代 春節会」なる展覧会を観てきました。田中宗慶作黒楽茶碗初雪、三代道入作黒楽茶碗早梅、六代左入作赤楽茶碗桃里、等々。
これまた偶然ですが、楽美術館のすぐ近くにあった岩元禄の名建築「西陣電話局」(1920年・大正9年)を観ることができました。岩元禄は伝説の建築家で、生涯に3作しか設計しなかったと言われています。29歳の若さで肺結核により死去。今回何度も通った原広司設計の「京都駅」も観てきました。「京都駅」はコンペの発表会の時も京都まで観に行きましたし、出来てからも何度か観に行きました。.ヤマトインターナショナルや、飯田市美術博物館など、原さんの建築も過去にあちこちと観て歩きました。
忘れていることもあるかと思いますが、とりあえず忘れないうちにここに書き留めておきます。詳細は後日、少しずつ載せる予定でおります。
愛知県美術館で「クリムト 黄金の騎士をめぐる物語」を観た!
愛知県美術館で、開館20周年記念 生誕150年記念「クリムト 黄金の騎士をめぐる物語」を観てきました。愛知県美術館へは開館してすぐに友人に連れられて行った記憶がありますが、なにを観たのかは覚えていません。ですから始めて行ったようなものです。「クリムト 黄金の騎士をめぐる物語」は、宇都宮美術館へも巡回することは知っていましたが、少しでも早く見たいと思い、名古屋まで行ってきました。ウィーン分離派展ポスターや、ウィーン工房の作品は過去に何度か観ているので、ここではほとんど取り上げていません。
今回、チャールズ・レイニー・マッキントッシュの「室内装飾の芸術家『芸術愛好者の家Ⅱ』」の設計図面(リトグラフ)が出ていて、興味を持ちました。またマーガレット・マクドナルド・マッキントッシュの「2枚1組の刺繍パネル」は、マッキントッシュが設計した「ヒル・ハウス」の室内装飾の一部であったと、図録に書かれていました。建築を始めた頃からマッキントッシュの設計した「グラスゴー美術学校」へ行ってみたいと思っていましたが、未だに実現していません。この歳になっても、憧れだけが募ります。
今回初めてウィーン大学大講堂の天井装飾画を原寸大で観ることができました。「神学」「哲学」「医学」「法学」が天井の4隅に配される予定だったというが、大学評議会を通じて文部大臣に講義の請願書が提出され、スキャンダルになりました。今回は「哲学」「医学」「法学」の3点が原寸大写真パネルで展示されていました。クリムトの代表作でもある「ベートーヴェン・フリーズ」部分の原寸大写真パネルが展示されていました。ウィーンの分離派館の地下にあるこの作品、壁画ですが、僕は行ったことは行ったのですが、観た記憶が抜け落ちています。
Ⅱ章では、今回の目玉、愛知県美術館所蔵の「人生は戦いなり(黄金の騎士)」が出ていました。デューラーの銅版画「騎士と死の悪魔」を下敷きにした作品といわれています。「ベートーヴェン・フリーズ」において人々を幸福へと導いた騎士は、「人生は戦いなり(黄金の騎士)」では、自らの芸術の理想を追求する芸術家の姿により明確に重ね合わされる、と図録では解説しています。また、クリムト作品としては異質な風景画「アッター湖畔」が出ていました。水面のさざ波を表現する短い筆致は、モネなどの印象派の手法を想起させます。
「ストックレー・フリーズ」下絵については、会場の最後に、原寸大写真パネルで展示されていて、写真撮影が唯一オーケーな箇所でした。ウィーン工房の作品については、ヨ-ゼフ・ホフマンの椅子を始め、さまざまな作品が展示してありましたが、小さな作品ですがやはりユーゼフ・ホフマンの「ブローチ」が好印象を持ちました。ジャポニスムとして鈴木基一の「秋草図」六曲一隻などが出ていました。
Ⅲ章では、オスカー・ココシュカのポスターや、版画集「夢見る少年たち」等の作品の他、「オイゲニア・プリマフェージの肖像」や「赤子(揺りかご)」など、クリムトらしい作品が並んでいました。
Ⅰ願いへのプレリュード―ウィーン工芸美術学校入学から分離派結成へ
Ⅱ黄金の騎士をめぐる物語―ウィーン大学大講堂の天井画にまつわるスキャンダルから「黄金の騎士」誕生へ
Ⅲ勝利のノクターン―クンストシャウ開催から新たなる様式の確立へ
「ストックレー・フリーズ」下絵、実物大複製での展示
生誕150年記念
「クリムト 黄金の騎士をめぐる物語」
ウィーンの世紀末美術を代表する画家グスタフ・クリムト(1862-1918年)。その甘美で装飾的なスタイルは、今なお多くの人を魅了し続けています。愛知県美術館の開館20周年を記念して開催する本展では、国内外のコレクションによるクリムトの油彩画約10点、素描約30点を中心に、クリムトと深く関わった工芸職人の生産組合ウィーン工房の作品などもあわせて展示します。愛知県美術館の所蔵するクリムト《人生は戦いなり(黄金の騎士)》は、様々な謎が秘められた作品です。本展では、「黄金の騎士」誕生の謎を解き明かす物語から、芸術家クリムトの歩んだ道をたどる物語へと皆さまをご案内します。この物語を通して、クリムト芸術の新たな面を発見していただけることでしょう。
「クリムト 黄金の騎士をめぐる物語」
図録
編集:愛知県美術館
長崎県美術館
宇都宮美術館
中日新聞社
発行:中日新聞社
©2012
過去の関連記事:
パナソニック電工汐留ミュージアムで「ウィーン工房1903-1932」展を観た!
松屋銀座で「アール・ヌーヴォーのポスター芸術展」を観た!
ウィーン分離派の建築家と建築!
日本橋高島屋で「クリムト、シーレ ウィーン世紀末展」を観た!
オットー・ヴァーグナーの「ウィーン郵便貯金局」を観た!
以下は、僕が手元に置いてよく眺めている本の一部です。順不同
建築巡礼10
「世紀末の中の近代
オットー・ワーグナーの作品と手法」
著者:越後島研一
平成元年3月30日発行
丸善株式会社

建築巡礼13
「ウィーンの都市と建築
様式の回路を辿る」
著者:川向正人
平成2年4月30日発行
丸善株式会社

「世紀末ウィーンを歩く」
池内紀 南川三治郎
新潮社とんぼの本
発行:1987年3月25日
図説「クリムトとウィーン美術散歩」
南川三治郎
河出書房新社
発行:1998年10月13日
新潮美術文庫37
著者:飯田善国
編者:日本アートセンター
発行:昭和50年12月25日
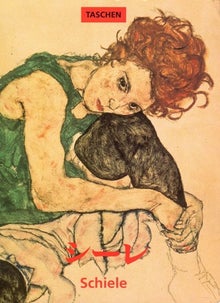
TASCHEN
「シーレ Schiele」
Egon Schiele 1890-1918
真夜中の魂
ラインハルト・シュタイナー
Benedikt Taschen
京都・細見美術館で「江戸絵画の至宝 琳派と若冲」を観た!
京都・細見美術館で「江戸絵画の至宝 琳派と若冲」を観てきました。京都を訪れたらぜひ行ってみたいと思っていた美術館、やっと念願が叶いました。細見コレクションと言えば、琳派の作品を数多く所蔵していることで知られています。多くの「琳派展」にコレクションを貸し出したりもしています。また東京でも「細見美術館」と銘打った展覧会が開かれています。僕が最初に細見美術館の作品と出会ったのは、日本橋高島屋で開催された「日本の美びと出会う―淋派・若冲・数寄の心―」でした。図録には「細見美術館開館10周年記念展」とあります。
今回の「江戸絵画の至宝 琳派と若冲」は開館15周年記念特別展とあります。もう5年も経ってしまいました。去年はそごう美術館で京都・細見美術館展として、「都の遊び・王朝の美」と「琳派・若冲と雅の世界」を観ることができました。もちろん「琳派」といっても幅広い世界です。今回は俵屋宗達、尾形光琳、中村芳中、酒井抱一、鈴木基一らの作品がありました。そして「琳派と若冲」というタイトルにもある通り、伊藤若冲の作品が17点(前期)出ていました。若冲といえば「鶏図」、多くの「鶏図」が出ていました。ここでは「雪中雄鶏図」と「鶏図押絵貼屏風」、そして「風竹図」を載せておきます。
展覧会の構成は、以下の通りです。
華麗なる琳派
若冲の魅惑
琳派の美しき世界
華麗なる琳派
若冲の魅惑
細見美術館
開館15周年記念特別展
「江戸絵画の至宝 琳派と若冲」
初代 古香庵(1901~1979)に始まる細見コレクションは、日本美術史を辿ることのできる多様な作品からなります。記念特別展の第1弾となる本展では、江戸時代の中でも極めて魅力に富む琳派と伊藤若冲の作品をご紹介します。 俵屋宗達から酒井抱一らに至る琳派の華麗な様式と、伊藤若冲の独創的な画風が味わえる、細見コレクションならではのラインナップをお愉しみください。
「琳派・若冲と雅の世界」
2010年10月20日初版発行
監修:細見美術館
発行所:株式会社青幻舎
 細見美術館開館10周年記念展
細見美術館開館10周年記念展
「日本の美びと出会う―淋派・若冲・数寄の心―」
図録
編集:細見美術館
制作・発行:毎日放送
過去の関連記事:
そごう美術館で「京都・細見美術館展 都の遊び・王朝の美」を観た!日本橋高島屋で「日本の美と出会う―淋派・若冲・数寄の心―」展を観た!
山梨県立美術館で「ミレー館(常設展)」を観た!
山梨県立美術館で「ミレー館(常設展)」を観てきました。といっても行ったのは去年の12月12日のことです。ブログに書くのに、1ヶ月以上も過ぎてしまいました。実は秋の紅葉の時期に昇仙峡を観て、山梨県立美術館でミレーの作品を観ようと思っていたのですが、毎度のことですが、観に行くのがズルズルと遅れてしまったというわけです。ふと思い出して本棚を探ってみたら、「山梨県立美術館 蔵品抄」が出てきました。しかもこれは「開館記念」と表紙に印刷されている超レアものです。日付を見ると、1978年、昭和53年11月とあります。今から35年も前の話です。
その頃数年にわたり、仕事で山梨を訪れていました。そうしたことから開館してすぐに美術館を見ることが出来たのでしょう。今思い出すとその他にも、建築士会の見学会とか、事務所の見学会とかで、山梨県立美術館を訪れていました。当時の山梨県知事は田辺国男さんで、前川事務所に設計を依頼したとき、ルーブル美術館のような美術館にして欲しい、と言ったと、設計を担当した大宇根弘司さんから聞いたことがあります。ちなみに大宇根さんは、山梨の数年後に宮城県立美術館も担当していたようです。前川事務所から独立してからは、町田市国際版画美術館などを設計しています。
昭和47年に置県100年記念事業として県立美術館の建設を決定します。ミレーを軸にバルビゾン派の作品を蒐集する方針が決定されます。アメリカでの競売で「種まく人」と「夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い」の油彩画2点を計1億820万円で落札しました。名作が落札されたニュースは大々的に報道されます。それに対する意見も、賛否両論がおきました。開館当初からミレーファンが殺到し、空前のミレーブームが起こりました。最近では2011年に、コレクションの中で不足していたミレーの風景画を購入しました。それはさておき、ミレーの美術館として知られる山梨県立美術館、ミレーの収蔵作品は、油彩画11点を含む約70点のコレクションになり、今回それらが一挙公開されていました。所蔵作品を一度に公開するのは1978年の開館以来初めてのことで、絶好の機会でした。
ジャン=フランソワ・ミレーの生涯
ジャン=フランソワ・ミレーは、1814年にフランス北西部のグリュシー村で生まれました。小さい頃から絵を描くのが好きだったミレーは、パリの美術学校へ通い、プロの画家なります。1849年には、パリから少し離れたバルビゾン村に移住。この村で最初に描いた大作が、「種をまく人」でした。1875年に亡くなるまで、ミレーはバルビゾン村に住み続け、農民の姿や生活を描きました。
バルビゾンの画家たち
パリから60kmほど離れたところに「フォンテーヌブローの森」という大きな森があります。その森のまわりにある森のひとつがバルビゾン村です。19世紀前半、この村にはミレーを含めてたくさんの芸術家が集まっていました。彼らは、この村の名前をとって「バルビゾン派」と呼ばれています。
ミレーの作品
風景画の系譜(クロード・ロラン~バルビゾン派)
「ミレーに出会える美術館」
2点の油彩画から出発した当館のミレーコレクション。1978年の開館時より一貫した収集方針の結実として、現在は油彩画11点を含む約70点のコレクションへと成長いたしました。これは、ミレーを所蔵するフランスやアメリカの代表的な美術館と比べても、非常に充実したものと言えます。これらを一挙公開し、ミレーの作品の豊かな世界を紹介する展覧会を開催いたします。
 「山梨県立美術館名品選(第二版)」
「山梨県立美術館名品選(第二版)」 編集・発行:山梨県立美術館©2006
制作:京都便利堂
編集:山梨県立美術館
井出洋一郎 小野迪孝
佐藤徹郎 守谷正彦
発行:山梨県立美術館
©1978
製作:便利堂
山梨県立美術館の屋外彫刻を観た!
芸術の森公園は、その中に山梨県立美術館と山梨県立文学館をふくみ、随所に彫刻を配置した公園です(6.0ha)。バラ園や日本庭園、ボタン園もあり、手入れの行き届いた公園は四季折々の表情で、訪れる人々の目を楽しませてくれます。
ここでは山梨県立美術館の屋外に展示されている彫刻を取り上げてみたいと思います。その中でも特に注目されるのは「バルビゾンの庭」です。その入口にアンリ・シャピュの「ミレーとルソーの記念碑」が設置されています。その横の銘板に、以下のような“いわれ”が書かれていました。
J・F・ミレー(1814-1875 右)とTH・ルソー(1812-1867 左)はバルビゾン派の中心的存在として創作に励み、するレ田芸術作品を数多く残しました。このレリーフは、二人の功績を称えるために若い画家の発起によって制作され、1884年以降フォンテーヌブローの森の入口に置かれています。今回バルビゾン村のご厚意により原型からの忠三を許され、山梨県立美術館開館15周年を記念してここに設置をみたものです。ちなみに1850年頃、ルソーたちは政府が打ち出したフォンテーヌブローの森の開発計画に反対し、その結果美観保護林が設定され、これを記念する碑文もその傍らに添えられていました。これが国際的な自然保護運動の始まりとも言われています。1993年11月4日
山梨県立美術館の屋外に展示されている彫刻でもっとも注目されるのは、山梨美術館の正面に配置されているヘンリ・ムアの巨大なブロンズ彫刻「四つに分かれた横たわる人体」で、高さは台座を含めると213cmもあります。図録の解説には以下のようにあります。「彼は芸術活動を通じて一貫して横たわる像を造りつづけた。はじめは具象的なものからしだいに抽象的なものになって行き、当初1体であったものが年代を経るとともに2つ3つとわかれて行き、遂に4つに分かれた。「四つに分かれた横たわる人体」は、ムアの生涯のテーマが極度に抽象化し構成的なものになった、その到達点というべき作品である。」
他にもロダンやマイヨール、ブールデルやザッキンなど、興味深い作品が並んでいます。また生涯の親友であった舟越保武と佐藤忠良の作品も近くに並んでありました。
 「山梨県立美術館名品選(第二版)」
「山梨県立美術館名品選(第二版)」 編集・発行:山梨県立美術館©2006
制作:京都便利堂
過去の関連記事:
トレドで観たエル・グレコ!
1月19日から始まった「エル・グレコ展」のチラシを見ていたら、マドリッドのプラド美術館でエル・グレコの作品を何点か見たことを思い出しました。2007年12月14日から21日まで8日間、スペイン各地を見て回るツアーに行ったときのことです。最終日だったか、トレドにも行きました。サント・トメ教会でエル・グレコの代表作と言われている「オルガス伯爵の埋葬」も観た記憶があります。
代表作「オルガス伯の埋葬」は、トレドのサント・トメ教会の注文で制作したもの。楯のような画面を上下に二分割し、地上界の埋葬シーンにはひそやかな動き、魂が昇天する場―天上界―には派手な動きを与え、また地上界には当時トレドに実在した名士たちをずらりと並べるユニークさによって、この絵は大きな評判を呼んだ。(中野京子著「名画で読み解くハプスブルグ家の12の物語」光文社新書:2008年8月15日初版1刷発行)
スペイン旅行の画像を見直してみたら、サント・トメ教会の画像が見当たりません。「オルガス伯爵の埋葬」は写真撮影禁止だったようですが、入口廻りや、表示版のようなものを写真に撮った記憶がありますが、画像が見当たりません。残っていたのは、スペイン・カトリックの総本山「カテドラル」の画像が10数枚だけでした。
その中にエル・グレコのキリストの衣の赤が鮮烈な「聖衣剥奪」がありました。実はこの絵の題名が分からなくて、ブログに載せるのを躊躇していましたが、宮下規久朗編著の「不朽の名画を読み解く 見ておきたい西洋絵画70選」(2010年8月1日初版発行)を見ていたら、なんとエル・グレコの「聖衣剥奪」が載っていました。ちなみに同じ宮下規久朗の「知っておきたい世界の名画」(角川ソフィア文庫:平成24年1月25日初版発行)にも載っていました。
キリストは十字架にかけられる前に刑場で身につけていた衣をはぎとられた。その衣を兵士たちは賭けをして奪い合ったという。キリストの真っ赤な衣は今まさに荒々しくはぎとられようとするところで、その赤色は隣の男の甲冑に反映している。キリストは胸に手をあて、天を見上げている。画面下には、十字架が準備されており、それを3人のマリアが見ている。(宮下規久朗の「知っておきたい世界の名画」より)
そんなわけで、トレドの「カテドラル」と、エル・グレコの「聖衣剥奪」を以下に載せておきます。
過去の関連記事:
イーユン・リーの「黄金の少年、エメラルドの少女」を読んだ!
イーユン・リーの「黄金の少年、エメラルドの少女」(河出書房新社:2012年7月30日初版発行)を読みました。本の帯には、短篇の名手イーユン・リーの「千年の祈り」(映画化)に続く最新短篇集、とあります。イーユン・リーの作品は、デビュー作の短篇集「千年の祈り」ともう一つ、「さすらう者たち」という長編を読みました。「さすらう者たち」のブログに書いたものを読み直してみると、発売と同時に購入して読んだが、なかなかブログに書くことが出来なかった、というようなことが書いてありました。今回もまったく同じで、去年の夏に購入し、一度読み、そして暫く間をおいて再度読みましたが、なかなかブログには書けませんでした。
イーユン・リーの略歴は、以下の通り。
1972年北京生まれ。北京大学卒業後に渡米、アイオワ大学大学院で免疫学の修士課程を終えた後に方向転換し、同大学の創作科に入学して英語で執筆するようになる。2005年に発表した短篇集「千年の祈り」で、フランク・オコーナー国際短篇賞、PEN/ヘミングウェイ賞、ガーディアン新人賞などを受賞。また文芸誌「グランタ」で「アメリカでもっとも有望な35歳以下の作家」の一人に選ばれた。現在はカリフォルニア大学デービス校で創作を教えながら執筆を続けている。文芸誌「ア・パブリック・スペース」の寄稿編集者の一人でもある。夫と二人の子供とともに、カリフォルニア州オークランドに暮らす。
篠森ゆりこは「訳者あとがき」で、以下のように述べています。
本書に収められた作品の大半は、大きな転換期を迎えて変貌著しい現代中国を舞台にしている。登場人物が時代や場に束縛されている感があった前作の短篇集と違い、本作では人々がむしろ拠りどころを失い、孤独を深め、過去を懐かしんですらいるようだ。そうして明かされる過去の記憶は、過ぎていく現在と溶け合うように綴られ、たとえ忌まわしい記憶であっても美しさを感じさせる。同時に、未来にじっと目をこらせば必ずなんらかの灯が見え、読後感が優しい。
「黄金の少年、エメラルドの少女」には、イーユン・リーによって英語で書かれた、やや長いのも短いものもありますが、以下の9篇が収められています。
・優しさ
・彼みたいな男
・獄
・女店主
・火宅
・花園路三号
・流れゆく時
・記念
・黄金の少年、エメラルドの少女
一つ一つ作品を見てみましょう。
「優しさ」は、この短篇集の中でも最も長いものです。41歳の独り暮らしの女が主人公です。三流の中学校で数学を教えています。人に心を開くことの出来ない独身女性が、一人で生きていく決意をするに至った過去を回想する物語です。父は20歳も年下の気が触れた母を嫁にもらい、それを見て私は育ちます。ある時、自分が養子であることを、近所に住む心を許した英文学を教えてくれた杉(シャン)教授から知らされます。また軍隊の訓練時代を振り返り、上官だった魏(ウェイ)中尉を思い出したりもします。二人とも、もう亡くなっています。軍隊時代の同僚で歌の上手かった南(ナン)の顔ををテレビで見かけたりもします。
「彼みたいな男」は、年老いた母親と2人暮らしの独身の元美術教師、費(フェイ)師が、共産党員の父親の不倫を激しく告発する実の娘のブログに、自らの辛い過去を思い出し、友情を感じて娘の父親に会いに行きます。費師の父は、文革で大学教授から便所掃除人に降格されて費師の教育は終わります。父は大学の教職に戻されてから2年目に自殺しました。彼みたいな男とは、週に3回、母親を風呂に入れてくれる羅(ルオ)夫人が、費師が羅夫人に夕方までいてくれるように頼んだときに羅夫人が言った言葉、「確かに費師みたいな男性はときには恒例のご婦人の介護から解放されるに値しますよ」からきています。
「獄」は、16歳の娘を交通事故で失った、裕福でインテリの在米中国人夫妻が、母国の農村で代理母を求め、再び子どもを得ようとします。息子を失った健康な若い女性を代理母に選び、子供が生まれるまで一緒に暮らします。代理母の胎内にいる子供をめぐって、二人は互いの囚人なのだと思います。ある日、二人で町へ出かけると、行方不明になった息子と思われるぼろを着た男の子を見て彼女は「名前はなんだい。年はいくつ。親はどこ。家は」と問いただします。彼女は、自分が育てるよりもいい暮らしが出来ると信じて、息子を売ったのでした。
「女店主」は、拘置所前のよろず屋の女店主である金(ジン)夫人は68歳、2年前に夫が亡くなり未亡人になった。恵まれない女性たちに手をさしのべて同居しています。死刑囚の夫との子供を残したいと、処刑前の子づくりの権利を申し立てた若い女性を保護する金夫人は、上海の若い女性記者から取材されることになりました。
「火宅」は、6人は公園で母親同士として知り合い、婚外恋愛に宣戦布告して、浮気夫たちの素行を調べる探偵になることにしました。6人は親しい付き合いを続けてきたが、その女性たちにもそれぞれの過去がありました。6人の老女が私立探偵として成功したという話題が新聞記事になり、テレビ局が短篇ドキュメンタリーとして取り上げました。それを見て、男性の依頼主が現れました。妻と父親の不倫を疑って相談に来た男の訴えを聞いて、彼女たちの団結は揺らいでいきます。
「花園路三号」は、45年前の少女時代に憧れた男性が妻を失ったことを知った女性の心情を描いています。
「流れゆく時」は、義姉妹の契りを結んだ3人の少女たちは、50年後には憎しみ合うようになっていました。それぞれが結婚して得た息子と娘を結婚させようと思っていたのに、息子が娘を殺してしまい、死刑になってしまった事件があったのです。しかし、一番にくまれているのは、事件と無関係だった主人公でした。
「記念」は、今は精神を病む天安門事件の元ヒーローの恋人に会いに行く女性の悲しさを描いています。
表題作「黄金の少年、エメラルドの少女」は、同性愛の対象だった38歳の女性を42歳になるゲイの息子の嫁にしようと思う老女教授。かつては理想的な「金童碧女」と呼ばれたであろう夫婦の娘だった女性は、新たな家族を築く決意をします。中国では理想のカップルを「金童(ゴールドボーイ)碧女(エメラルドガール)」というそうです。
朝日新聞の書評(2012.9.16)で小野正嗣は、以下のようにいいます。
各編からは、一人っ子政策の歪み、人権問題、爆発的な経済成長と増大する社会的経済格差、加熱するネット社会といった、昨今各種メディアでよく報じられている中国社会の姿が垣間見えてくる。・・・だが、欧米の読者を意識してか、あるいはアメリカで英語で書くことで、本国では書きにくい主題により自由に向き合えるからか、やや批判精神の立ち勝る眼差しで中国が見つめられていたように思う。・・・だが、そうした問題が、登場人物たちのそばに確かに感じられつつも、固有の苦悩と喜びを抱えた魂の動き、つまり一人一人の人間に触れることを妨げていないところに本書の身震いするほどの完成度はある。
また、読売新聞の書評(2012.9.24)で角田光代は、以下のようにいいます。
どんな衝撃的な関係も、絶望的な状況も、作者はごくふつうの日常として淡々と描く。そこここに「やさしさ」がちりばめられている。これも孤独と同様、作者は絶妙に描き分ける。人生を賭けた壮絶なやさしさがあり、恋愛によく似たやさしさがあり、残酷なやさしさが、軽い挨拶のようなやさしさがある。善意とは異なるそのやさしさは、過酷な人生を救いはしない。孤独をいやすこともない。ただ、ある。やさしさという言葉の定義を越えて、ただ、あり、そのことに私は力づけられる。
過去の関連記事:
イーユン・リーの「さすらう者たち」を読んだ!
イーユン・リー原作の映画「千年の祈り」を観た!
イーユン・リーの「千年の祈り」を読んだ!
クリスティアン・ペッツォルト監督・脚本「東ベルリンから来た女」を観た!
33年前の旧東ドイツ。秘密警察に監視されながら西側への逃亡を図る女性医師を描く「東ベルリンから来た女(原題:バルバラ)」を観てきました。たとえば傑作と誉れの高い「善き人のためのソナタ」を始め、「東ドイツもの」も出尽くした感がありますが、そうはいっても1989年11月9日にベルリンの壁が崩壊して、はや24年も経ち、新たな視点で東ドイツを描いた傑作が生まれました。東ドイツと言えば、短絡的かもしれませんが、猜疑心の渦巻く時代の秘密警察(シュタージ)の存在を忘れることはできません。
1980年夏、旧東ドイツ、バルト海沿岸の田舎町の病院に一人の美しい女医が来ました。彼女の名はバルバラ。かつては東ベルリンの大病院に勤務していたが、西側への移住申請を政府にはねつけられ、秘密警察(シュタージ)の監視付きで、この地に左遷されてきたのでした。新しい病院の同僚アンドレから寄せられるさりげない優しさにもシュタージへの密告ではないかと猜疑心が拭いきれません。西ベルリンで暮らす恋人ヨルクとの秘密の逢瀬や、自由を奪われた毎日にも神経がすり減っていきます。そんなバルバラの心の支えとなるのは患者への献身と、医者としてのプライドでした。同時にアンドレの誠実な医師としての姿に、尊敬の念を越えた感情を抱き始めます。しかし、ヨルクの手引きによる西側への脱出の日は、刻々と近づいてきます。
ペッツォルト監督は旧西独生まれだが、両親は1950年代に旧東独から逃亡してきました。東の小さな村に住む祖母ら親類や友人を毎年夏に訪ねたという。「東は監獄のような国歌だったが、私たちにとっては同時に夢の中の世界だった記憶もある」と語っています。東西ドイツ統一後、旧東独は映画などで「暗い灰色の社会」と類型的に示されることが多いのが気になっていた、とペッツォルト監督はいう。自らの記憶や徹底した調査から、当時の東独の田舎町と人々をリアルに描いた、という。いずれにせよ、東独時代の記憶は、人々にとって「癒えるのに非常に長い時間を要する傷」であると言われています。
ヒロインのバルバラ役を演じた美貌の女優ニーナ・ホスです。いや、いい女です。彼女がいてこそこの映画が成立した、と言っても過言ではないでしょう。その傑出した演技で、バルバラの魂の叫びを体現しました。颯爽と自転車に乗るところがいい。一方、相手役の医師アンドレは、小太りの、決してイイ男とは言えませんが、誠実さをその存在と身体で表現していました。東西ドイツが統一されて20数年の歳月が流れました。西側への脱出の日が刻々と近づくなかで、バルバラが下す最後の決断は・・・。
以下、とりあえずシネマトゥデイより引用しておきます。
チェック:ドイツの新鋭クリスティアン・ペツォールトが監督と脚本を担当し、旧東ドイツで疑心暗鬼に駆られつつ生きる女医の姿を描いた衝撃作。ベルリンの壁崩壊前の不自由な時代、厳しい監視の目をかいくぐって脱出を試みようとするヒロインの揺れ動く感情を牧歌的な風景と共に描き出す。美ぼうの下に情熱を秘めた主人公を演じるのは、『ブラッディ・パーティ』のニーナ・ホス。苦難の日々の中で、もがきつつも必死に生き抜こうとする女性の姿に涙があふれる。
ストーリー:1980年夏、医師のバルバラ(ニーナ・ホス)は東ベルリンの大病院からバルト海沿岸にある小さな町の病院に赴任する。西ドイツへの移住申請を却下され左遷された彼女は、上司のアンドレ(ロナルト・ツェアフェルト)にも笑顔ひとつ見せず同僚とも打ち解けようとはしなかった。そんなある日、矯正収容所から逃げようとするも病気になってしまったステラ(ヤスナ・フリッツィー・バウアー)が運び込まれ……。
過去の関連記事:
映画「善き人のためのソナタ」を観た!名古屋名物を食べる!
名古屋名物で美味しいものと言ったらきしめん、天むす、小倉トースト、どて煮、あんかけスパゲッティ、イタリアンスパゲッティ、味噌おでん、味噌カツ、手羽先唐揚げ、台湾ラーメン、エビフライなど数々ありますが、なんといっても「味噌煮込みうどん」と「ひつまぶし」でしょう。名古屋から帰ってきたとき、ブログに以下のように書きました。
名古屋へ行ったら、まずは昼は山本屋本店の「味噌煮込みうどん」、夜はあつた蓬莱軒の「ひつまぶし」を食べること。「味噌煮込みうどん」は名古屋の友人に連れて行ってもらい食べたことがありますが、「ひつまぶし」は初体験でした。そして近鉄の前のナナちゃんを見ること、ナナちゃんは愛・地球博のときに見ていましたが、再び見てきました。
帰ってから知ったのですが、山本屋の味噌煮込みうどんは二つあるんですね。一つは山本屋本店、もう一つは山本屋総本家、今回僕が行ったのは山本屋本店、以前名古屋の友人に連れて行ってもらったのはどうも山本屋総本家だったようです。
名古屋名物味噌煮込みうどん対決!「山本屋本店」VS「山本屋総本家」
「山本屋本店」名古屋駅前店
「あつた蓬莱軒」松坂屋店
「ひつまぶしの食べ方」YouTube
番外編:ナナちゃん
過去の関連記事:
大倉集古館で「画の東西~近世近代絵画による美の競演・西から東から~」を観た!
大倉集古館で、館蔵品展「画の東西~近世近代絵画による美の競演・西から東から~」を観てきました。観に行ったのはお正月気分が抜けきれぬ1月3日のことでした。
大倉集古館と言えば、僕の中では「追憶の羅馬展 館蔵日本近代絵画の精華」、その時に出されていた横山大観の「夜桜」と前田青邨の「洞窟の頼朝」です。この二つの傑作を所蔵しているんですね、大倉集古館は。今回の「画の東西」、後期、2月19日から大観の「夜桜」が出てきます。
今回の目玉はなんと言っても横山大観の「瀟湘八景」でしょう。これもやはり「追憶の羅馬展 館蔵日本近代絵画の精華」に出されていました。大倉集古館蔵の「瀟湘八景」は、「山市晴嵐」「遠浦帰帆」「洞庭秋月」「瀦湘夜雨」「姻寺晩鐘」「漁村返照」「平沙落雁」「江天暮雪」です。8幅のうち、前期は「洞庭秋月」「瀟湘夜雨」「姻寺晩鐘」の3幅、後期は「漁村返照」「平沙落雁」「江天暮雪」の3幅が展示されます。
横山大観の「瀟湘八景」は大倉集古館だけではなく、茨城県立美術館蔵の「瀟湘八景」があります。また国立博物館でも所蔵しています。
国立博物館の「瀟湘八景」は、大正元年(1912)第6回文展に出品されたもので、中国旅行より帰った直後の成果であり、古来親しまれた東洋画の主題にいどみつつ、その伝統に対し大観独自の新解釈を示した記念的作品である、といわれています。 大観の「瀟湘八景」について、夏目漱石の「文展評」をネットで見つけました。
「大観君の八景を見ると、…横山大観に特有な八景であるといふ感じが出てくる。君の絵には気の利いた様な間の抜けた様な趣があって、大変に巧な手際を見せると同時に、変に無粋な無頓着な所も具へている。君の絵に見る脱俗の気は高士禅僧のそれと違って、もっと平民的な呑気なものである。八景のうちにある雁は丸で揚羽の鶴の様に無格好ではないか。さうして夫が平気でいくつも蚊のように飛んでゐるではないか。さうして雲だか陸だか分らない上の方に無造作に並んでゐるではないか。またいかにも屈託がなさそうではないか。…」(新聞評論『文展と芸術』夏目漱石)
横山大観「瀟湘八景」
その他の作品
「画の東西~近世近代絵画による美の競演・西から東から~」
当館の所蔵する多彩な日本絵画の作品を、それらが生まれた地域を西・東に分けて陳べるという角度からご鑑賞頂く試みです。京を中心とする西からは狩野派の山口雪渓や円山四条派の円山応挙と呉春、近代京都画壇の雄・竹内栖鳳、また活動の初期を四条派に学んだ川合玉堂などの画業を展観します。一方、江戸に拠を移した東の作例としては、探幽を始めとする江戸狩野の画家と、その伝統を基に更なる発展を刻んだ横山大観等を選びました。西から東から、広がりながら継承されていく美の姿をお楽しみください。
「大倉集古館」ホームページ
過去の関連記事:
大倉集古館で「服部早苗 布工芸展」を観た!
大倉集古館で「煌めきの近代~美術からみたその時代」展を観た!
大倉集古館で「開窯300年マイセン西洋磁器の誕生」展を観た!
大倉集古館で「欣求浄土 ピュアランドを求めて~」展を観た!
大倉集古館で「爽やかな日本美術」展を観た!
大倉集古館で「花*華―日本・東洋美術に咲いた花―」展を観た!
大倉集古館で「追憶の羅馬展」を観た!
泉屋博古館で「吉祥のかたち」を観た!
「吉祥とは、幸い、おめでたい印、おめでたい萌し、よい前兆を意味します」と、解説にあります。新春には多くの美術館が「吉祥」をテーマとして取り上げたりして、お正月のいわば「定番」のテーマでもあります。僕もここ数年、お正月には「七福神めぐり」をしています。青銅器では龍、麒麟、鳳凰文、仙人など、絵画では松竹梅や鶴亀、花鳥など、幸福や長寿を祈って、「吉祥」は取り上げられてきました、と解説にあります。吉祥と言うことでは、陶磁器でしたが2010年の始めに、松岡美術館で「吉祥のうつわ 中国陶磁にみる祝い寿ぐ文様の世界」展を観ました。その時はまさに吉祥がテーマで、しかも懇切丁寧な解説で、わかりやすく展示してあったのを覚えています。
台北の「故宮博物院」や、上海の「上海博物館」、そしてソウルの「国立中央博物館」などを訪れて、「本場物」を観る機会がありました。当然のことですが、良質のものが嫌と言うほどゴロゴロありました。日本に来ているものは、その中のほんの一部です。青銅器に関しては、ほとんどが中国本土で出土したもの、あるいは伝来のものです。茶道具の「名物」もそうです。あるいは、絵画で言えばそうしたものを手本に描かれたものです。「吉祥」の言い伝えも、ほとんど中国で生まれ、朝鮮を通って日本に伝来したものです。
そう言って嘆いてばかりいても始まりません。僕の感じでは、日本に来ているもの、あるいは日本で描かれたものは、綺麗なものが多い、やはり洗練されていて、素晴らしいものばかりです。根津美術館も出光美術館も、そうしたものを所蔵して、競い合っています。静嘉堂文庫美術館も同じで、素晴らしいものを数多く所蔵しています。で、今回の目玉は、伊藤若冲の「海棠目白図」でしょう。今回のポスターやチラシにも取り上げられています。泉屋博古館のホームページに、以下のような解説がありました。
花盛りの四手辛夷(シテコブシ)と海棠。枝には身を寄せあう「目白押し」の仲間たちをよそ目に、瞑目するかの目白が一羽。伊藤若冲(1716-1800)は京都錦小路の青物問屋の主人だったが、絵に深く傾倒、40代で果行を譲り制作に専念した。鶏図をはじめとする濃彩の花鳥図や水墨画で異彩を放った。実物の観察を重んじた若冲らしく目白独特の生態に着目した本図は、鳥類を多く描いた彼の作品中でとりわけ愛らしく、小鳥への素直な共感が感じられる。落款から代表作「動植彩絵」に着手する前後、40代前半の作と考えられる。
いや~、お恥ずかしい、今気がつきました。いただいた「吉祥のかたち」の出品リストの裏側に、「主要文様の成立と伝来~中国から日本へ~」という資料が付いていました。中国の時代ごとの文様について、「饕餮文」「龍形文様」「鳥形文様」「虎、亀、筆不意などの動物文様」「吉祥文様」「四神文の発達」などの、詳細な解説が載っていました。ここでは「日本に伝来した吉祥文様」について二つ、以下の載せておきます。
★日本に伝来した吉祥文様1―不老長寿の象徴・神仙の世界
青銅鏡は、呪術力・霊力をもつものとされ、不老長寿、子孫繁栄、官位栄達などの願いを叶える道具として珍重された。たとえば、「西王母(せいおうぼ)」は日本でも謡曲などで広く知られており、三千年に一度実るとされる不老長寿の仙桃を携えている。また月の仙女「姮娥(常娥)」は、西王母の不老不死の霊薬を盗み飲んだことから身体が軽くなり、月に昇ったといわれる。「寿老人」は、中国における「日帝」または「南極老人」の化身とされ、天下太平の象徴、長生きと繁栄を司る神として七福神の一人となった。
★日本に伝来した吉祥文様2―梅にまつわる画題
日本人にとって、厳寒の中で百花にさきがけて清楚な花を開き、芳香を放つ梅の花は古の愛でられてきた。中国においては、文人の精神は象徴する歳寒三友、四君子、五清などの一つとして尊ばれ、四季花鳥画の中では、春を代表する花として多く描かれた。江戸時代から好んで描かれた「羅浮仙」は梅の精の伝説によるもので、中国広東省にある羅浮山で、一人の人士が芳香を放つ美女に出会い、楽しく酒を酌み交わしているうちに眠り込み、明け方目覚めたときには美女は消え、そこには梅樹があるのみだったというもの。日本において好まれた美しい羅浮仙の絵は、訪れた客人を華やかにもてなしたと思われる。
以下、チラシの裏面に載っていた画像を、絵画3点、青銅器3点、載せておきます。
「新春展 吉祥のかたち」
吉祥とは、幸い、おめでたい印、おめでたい萌し、よい前兆を意味します。中国の古代青銅器には、邪悪なものをよせつけないことを意図して文様が施されました。これが吉祥の文様となり、人びとはさまざまな文様に吉祥の意を託し、幸福や長寿を祈りました。龍、麒麟、鳳凰文、仙人など、青銅器や青銅鏡に施された文様は慶賀に満ち溢れています。日本では、中国から伝来した松竹梅や鶴亀、花鳥などが吉祥の意匠として定着し、お正月の床の間に、吉祥、つまり「おめでたい」ものを飾り、その1年が無病息災、多福多寿であることを祈念する風習が生まれました。本展では、泉屋博古館所蔵品からお正月を言祝ぐのにふさわしい吉祥の作品を選び、ご紹介いたします。
「泉屋博古館分館」ホームページ
過去の関連事:
泉屋博古館分館で「中国絵画 住友コレクションの白眉」を観た!
泉屋博古館分館で「近代日本洋画の魅惑の女性像」を観た!
泉屋博古館分館で「近代洋画と日本画」展を観た!
泉屋博古館分館で「幕末・明治の超絶技巧」展を観た!
泉屋博古館分館で「近代日本画にみる東西画壇」展を観た!
泉屋博古館分館(東京)で「住友コレクションの茶道具」展を観た!
泉屋博古館分館で「板谷波山をめぐる近代陶磁」展を観た!
泉屋博古館分館で「近代の屏風絵」展を観た!
トルナトーレ監督、モニカ・ベルッチ主演の「マレーナ」を(再び)観た!
最近のことですが、アクセス解析を見ると、映画「ダニエラという女」で検索して、このブログを見に来る方が大勢いることに気がつきました。言うまでもなく「イタリアの宝石」と言われているモニカ・ベルッチが主演した映画です。僕がモニカ・ベルッチを知ったのは、年上の女性に憧れる少年の物語、「マレーナ」(2000年)という映画です。その頃はまだブログを始めていなかったので、残念ながら記録としては残っていません。
その後、メル・ギブソンの「パッション」(2004年)という映画を観た後で、モニカ・ベルッチがマグダラのマリア役で出ていたのを知りました。最近では、イタリア系のロバート・デ・ニーロとモニカ・ベルッチが共演した、お気楽映画「昼下がりの、ローマの恋」(2011年)を観ました。モニカ・ベルッチの映画は、わずか数本しか観ていないのに気づきました。
中公新書、岡田温司著「マグダラのマリア エロスとアガペーの聖女」を読んだ時に、このブログに以下のように書きました。少し長いですが、引用します。
著者(岡田温司)は、「おわりに」の章で「生き続けるマグダラ」として三本の映画を提示します。メルギブソン監督の「パッション」(2004年)、ピーター・ミュラン監督の「マグダレンの祈り」(2002年)、そしてジュゼッペ・トルナトーレ監督の「マレーナ」(2000年)です。たまたま3本とも僕は観ていますが、この本を読んで「そうだったのか」と思い、納得することがありました。「パッション」についてこのブログに書いたときに、「受難」について意見の異なるコメントを、数々いただいたことも思い出しました。「マグダレンの祈り」は、アイルランドの女子更正施設、マグダレン修道院での現代の悲惨な悔悛の話です。マグダレンの名はマグダラからきています。「マレーナ」は、夫を戦争で失ったシチリアの女性マレーナ、マレーナはマッダレーナの愛称ですが、娼婦呼ばわりされる顛末を描いた作品です。ここでマレーナを演じた女優モニカ・ベッルッチは「パッション」でマグダラ役になっていたことも、当時話題になりました。いずれにせよ、表面的にしか観ていなかったこの3本の作品、この本を読んで理解が深まりました。もちろん映画だけでなく、西欧の美術に接するときには、この本を何度も開けて理解の手助けにしたいと思います。
映画「マレーナ」のストーリーは、以下の通りです。
時は第二次世界大戦、物語の舞台となるのはイタリア、シチリア島。主人公の少年レナートは12歳でありながら、自分より年上のマレーナに夢中でいた。マレーナは町中の男達にとって女神のような存在、しかしその反面町中の女性からは嫉妬の的であった。レナートは毎日がマレーナのことで頭が一杯であった。そして、できるだけマレーナに近付き、傍で見守ってきた。しかし、マレーナの夫はその後まもなく戦場に向かい、帰らぬ人となり、父親は空爆で命を落としてしまった。生きていく術を無くした彼女は徐々に自分の身を男達に投じていくようになる。時代の波と周囲の誹謗中傷にさらされる彼女を幼いレナートはただひたすら見守ることしかできなかった。(ウィキペディアより)
以下、とりあえずシネマトゥデイより引用しておきます。
チェック:その時ぼくは13歳。美しい人妻マレーナに夢中だった。『ニュー・シネマ・パラダイス』のトルナトーレ監督作。イタリア映画が好んで描く、年上の女性に憧れる少年の物語。なにより主演のモニカ・ベルッチが美しい。監督のトルナトーレは原作小説を気に入って長年構想を練っていたというが、ベルッチと出会った途端に映画化を具体的に進め始めたという。彼女がエレガントなスーツを身につけて港町を優美に歩く姿は異性ならずともスクリーンに視線が釘付け。彼女に憧れる少年役のスルファーロのコミカルな表情も楽しい。だが、陽の部分ばかりではなく人間の闇の部分にまで踏み込むあたりはトルナトーレ監督の本領発揮。
ストーリー:第二次大戦が開戦した年、少年(スルファーロ)は13歳になり、美しい人妻のマレーナ(ベルッチ)に恋をした。彼女の夫は軍人で出征中だった。だが彼が戦死したとの報を受け、街中の男たちが彼女に言い寄って、少年をやきもきさせる。
過去の関連記事:
「昼下がり、ローマの恋」を観た!
モニカ・ベルッチの「ダニエラという女」を観た!
「マグダラのマリア」を読む!
メル・ギブソンの「パッション」
李妍焱の「中国の市民社会―動き出す草の根NGO」を読んだ!
李妍焱の「中国の市民社会―動き出す草の根NGO」(岩波新書:2012年11月20日第1刷発行)を読みました。同じ岩波新書で、趙景達の「近代朝鮮と日本」と同時に購入したのですが、こちらは読むのが遅くなってしまいました。2年前でしたが、やはり岩波新書の「中国は、いま」を読みました。さまざまな問題はあるものの、中国も少しずつ変わり始めているのを実感しました。そうした現在の中国で、市民社会レベルでどのような変化が起きているのか、大いに興味があり、この本を手にしました。
以前、山崎亮の「コミュニティデザインの時代」を読みました。日本で、山崎は人と人とのつながりを基本に、地域の課題を地域に住む人たちが解決し、一人ひとりが豊かに生きるためのいコミュニティデザインを実践している活動家で、この本の中で日本の住民参加型の街づくりの歴史にも触れています。それをふまえて「中国の市民社会―動き出す草の根NGO」を読むと、中国と日本のNGO(非政府組織)/NPO(非営利組織)の展開は一方がもう一方を後から追う直線的なかたちではないことがよく分かります。
著者は、以下のように言います。NGO/NPOの展開の潮流は世界的であると同時に地域的であり、普遍的であると同時に個別的でもある。NGO/NPOのそれぞれの地域性と個別性に着目することによって、この分野が内包する多様性と豊かさをより理解し、より多くの可能性を弾き出すこともできるようになる、と。
公共の問題に対する民間の取り組みと動向は、その社会の変動を反映するだけではなく、その社会の今後の行方にも影響を与える。「先進―後進」の軸に収まることなく、、同じアジアの国として、中国のNGOの展開に目を向けることは、中国社会の変動を捉え、日本人が新たな視点に元ずく中国認識の第一歩となろう、と著者は述べています。
市民社会とは、非政府、非営利の立場から人々が自らのイニシアティブによって公共の問題について考え、行動する社会と、著者は定義します。公共問題に対する人々の参加の権利(法的・行政的保障)、参加の仕組み(場・ネットワーク)、参加の文化(参加する意識と習慣)という3つの歯車がかみ合い、動き出したときに、市民社会は大きく進展する、という。
第1章では、NGOの登場とダイナミックな活動展開を、改革開放後の中国社会の変化の節目に添って描き出しました。第2章では、NGOの実力と立場を強化し、人々の参加の意識と習慣を育んでいくためのNGO側の戦略を、その活動分野の背景とともに紹介しました。第3章では、公益領域を民間の手に取り戻すためのソーシャル・ビジネスの潮流を、社会変革につながるか否かを検討しています。
社会主義体制は、党と政府が公共問題のイニシアティブのすべてを握ることを特徴とします。にもかかわらず、異なる視点、異なる立場から公共問題に携わる「参加の仕組み」を創り上げようとするNGOなどの民間組織が、中国社会に現れたこと自体、社会主義体制の大きな変化を示唆している。中国はもはや、党と政府がすべてをコントロールする国ではなく、市民社会の活性化は、中国社会の多様化と活力につながる、と著者は述べています。
本のカバー裏には、以下のようにあります。
中国社会の問題に向き合う、草の根の非政府組織が力を伸ばしている。出稼ぎ農民工の支援、農村女性の教育と就労、環境調査と汚染追跡、住民参加のコミュニティ支援まで、知識人世代から若手起業家時代へと展開してきたその市民力に、国家も一目置かざるを得ない。地洞な日中交流を積む社会学者が、そのビジョンと知性、実践力を紹介する。
李妍焱の略歴を、以下に載せておきます。
1971年、中国・長春うまれ。1993年、吉林大学外国語学部日本語学科卒、東北大学大学院文学研究科人間科学専攻博士課程修了。専攻、社会学、NPO研究。現在、駒澤大学文学部社会学科准教授。日中市民社会ネットワーク(CSネット)代表。著書「ボランタリー活動の成立と展開」(ミネルヴァ書房)、共著「中国のNPO」(第一書林)。編著「台頭する中国の草の根NGO」(恒星社厚生閣)、共編「NPOの電子ネットワーク戦略」(東京大学出版会)。
目次
はじめに 「予想外」の中国へ
第1章 中国社会に「NGO人」登場
第2章 草の根NGOの戦略
第3章 ソーシャル・ビジネスの可能性と隘路
第4章 市民社会の底力
おわりに 個人として、そしてNGO人同士で
過去の関連記事:
山崎亮の「コミュニティデザインの時代」を読んだ!
国分良成編「中国は、いま」を読んだ!
京都国立博物館で「国宝十二天像と密教法会の世界」を観た!
京都国立近代美術館(槇文彦設計)には何度か行ったことがあるのですが、京都国立博物館を訪れるのは初めてのことです。京都国立博物館は赤坂・迎賓館を設計した宮廷建築家・片山東熊によるものです。2泊3日の名古屋・京都旅行の際に立ち寄ったのですが、特別展観「国宝十二天像と密教法会の世界」が開催されていました。まったく僕の苦手な分野ですが、なにはともあれ観ないことには始まりません。わけもわからず、観てきました。名古屋・京都から帰って、以下のように書きました。
さて京都の第二日目は、京都国立博物館で「特別展覧 国宝十二天像 密教法会の世界」を観てきました。同時開催として「成立800年記念 方丈記」がありました。国宝十二天像、いや、もう、第一室に展示されている「国宝十二天像」12幅をみただけで、ぐったりしてしまうほどでした。なにしろ国宝、重要文化財が目白押しですから、凄いのなんのって・・・。とはいえほとんど半分は分かりませんでしたが・・・。京都国立博物館、切符売り場の辺りから、これは谷口建築だなと思いました。ちょうど「新館?」が工事中で、その設計は谷口吉生の名前が出ていました。
新しい「平常展示館」のオープンは、平成26年春の予定だそうです。
それはさておき、特別展観「国宝十二天像と密教法会の世界」は、観るものすべてに圧倒されました。京都の新春の劈頭を飾る行事として著名な「後七日御修法(ごしちにちのみしほ)」は、正月7日までの宮中節会に引き続いて8日から14日まで7日間行われるもの。承和元年(834)、空海が宮中において天皇の安泰と国家の鎮護を祈るためにはじめて以来、一時的な中断はあるものの、現在でも場所を東寺の灌頂院に移して連綿と続けられているという。
京都国立博物館には、大治2年(1127)にこの修法のために新調された十二天像(国宝)が伝えられており、今回の展覧会は、十二幅すべてを一堂に展観し、後七日御修法の歴史を紐解く、というものです。また、平成24年は空海が日本で初めて本格的な灌頂を行って1200年に当たる記念の年でした。この重要な密教法会の歴史を知る上で、京都国立博物館所蔵の山水屏風や十二天屏風が展示されていました。
この展覧会では、空海が整備した密教法会の内、最も重要なものに数えられる宮中真言院後七日御修法や灌頂の儀礼を通じて、真言宗が守ってきた密教文化の精髄と、先人が鎮護国家に寄せた心に思いを馳せていただきたいと、京都国立博物館では展覧会の主旨を述べています。弘法大師空海については、図録に以下のような記述がありました。
密教修法が行われるようになったのは、弘法大師空海の力が大きい。弘法大師とは朝廷から与えられた尊称で、僧としての名が空海です。空海は讃岐の生まれ、18歳で都の大学寮(完了養成学校)に入ります。ところが仏教に心を寄せ、山中で修行をし、密教に触れたとされます。この東寺の密教は教理が整理されておらず、「雑密」と言います。空海はその後、延暦23年(804)に遣唐使に従って唐に渡り、密教を学ぶことになります。密教はインドでヒンズー教の影響を受け、遅く発生した仏教の一派で、中国に流入していました。「金剛頂経」を中心とする金剛頂系と、「大日経」を中心とする大日経系の二系統が重要であり、空海の師となった惠果は、これら亮流を教理的に統合した中国密教の第一人者でした。それは両界曼荼羅の世界に象徴されています(金剛頂系が金剛界曼荼羅、大日経系が胎蔵界曼荼羅)。空海は足かけ3年にわたる留学を終え、日本に正統な密教を伝えたのでした。これを「雑密」に対して「純密」と言います。空海は帰国後は、嵯峨天皇の信認を受け、高野山金剛峯寺を開創し、また弘仁14年(823)には東寺(教王護国寺)を下賜され、真言宗に礎を築いたのでした。
展覧会の構成は、以下の通りです。
第1部 国宝十二天像と後七日御修法
第1章 国宝十二天像
第2章 空海帰朝
第3章 後七日後修法のはじまり
第4章 後七日御修法の荘厳
第5章 後七日御修法のあゆみ
第2部 灌頂とその荘厳
山水屏風と十二天屏風を中心に
第1部 国宝十二天像と後七日御修法
第1章 国宝十二天像
承和2年(835)、空海の奏請によって正月8日から宮中真言院で7日間の修法が行われるようになりました。これを後七日御修法と言います。十二天像は道場を守護するために掛けられ、普段は道具類と一緒に東寺の宝蔵に収められていました。大治2年3月、東寺宝蔵は火災にあい、それまで使用されていた絵も消失してしまいます。この時新調されたのが本図です。この時の経緯は、「東宝記」巻二に詳細に説明されています。それによると、最初、東寺長者勝覚の命で、東大寺僧の覚仁は、小野経蔵 にかつて伝わり、宇治経蔵(平等院)に所蔵されていた弘法大師御筆様(空海スタイル)に基づいて調進したところ、鳥羽院から「疎荒(そこう)」との批判をこうむり、改めて仁和寺円堂後壁画に基づいて新写したという。前者を甲本、後者を乙本と区分しており、本図は乙本とみなされ、セットになる五大尊像とともに東寺に伝えられてきました。
第2章 空海帰朝
第3章 後七日後修法のはじまり
第4章 後七日御修法の荘厳
第5章 後七日御修法のあゆみ
第2部 灌頂とその荘厳
山水屏風と十二天屏風を中心に
特別展観「国宝十二天像と密教法会の世界」
承和元年(834)、空海は宮中で後七日御修法(ごしちにちのみしほ)を始めました。これは正月に行われる国家の鎮護を祈る修法で、現在でも東寺において続けられています。当館には大治2年(1127)にこの修法のため新調された十二天像が残されています。本展では、これを一堂に展示し、国宝山水屏風(当館蔵)など関連遺品とあわせて紹介します。後七日御修法と灌頂(かんじょう)という真言宗の重要法会を軸に密教文化の精髄に触れて頂きます。
図録
平成25年1月8日発行
編集:京都国立博物館
発行:京都国立博物館
同時開催「成立800年記念 方丈記」
鎌倉時代を代表する随筆として知られる「方丈記」は、鴨長明が建暦二年(1212)3月に執筆したもので、平成24年(2012)には成立800年という大きな節目を迎えます。これを記念して、現存最古の写本として名高い、大福光寺本「方丈記」(重要文化財)を中心に、関連する資料をあわせて展示します。
PR: 生命保険かんたん見直しシミュレーション
出光美術館で「オリエントの美術」を観た!
出光美術館で「中近東文化センター改修記念 オリエントの美術」を観てきました。中近東文化センターというと10数年前のこと、家人が、どういう団体かは知りませんが、中近東文化センターを見学したときに、三笠宮殿下に案内していただき感動した、と聞いたことがあります。中近東文化センターの建築は岡田新一の設計で、出来たときから知っていましたが、未だに行く機会がなくて、残念に思っていました。
出光美術館が1966年の開館時にはオリエント美術はコレクションの主要な一分野だったそうで、1979年秋以降は中近東文化センターで常時公開してきたようです。つまり、中近東文化センターは、出光美術館のオリエント美術の“別働隊”だったということになります。中近東文化センターの改修工事に伴い、今回、陶器・金属器・ガラス器・石製品などから厳選したオリエント美術の名品展を、34年ぶりに出光美術館で開催することになりました。先史時代からイスラーム時代にわたる幅広い年代で、石製品・土器・陶器・ガラス器・金属器など、時代・材質・地域においてこれだけ多岐にわたる作品と点数を一コレクションで提供できるのは、日本では出光美術館のみだと胸を張ります。これは凄いことです。
出光美術館の中近東美術は、エジプト・イラン・トルコ・地中海地域を中心に、多岐にわたる考古美術が充実しています。総数約3000点を数えるという。材質的には陶器(約500点)・土器(約350点)・ガラス製品(約350点)、そして青銅製品(約370点)等です。陶器ではイスラーム以降のイランのペルシア陶器(約450点)が最も多く、日本国内では珍しいトルコ陶器(約80点)が含まれています。
トルコ陶器では、イスタンブルの対岸の窯場イズニクやキュタヒヤで制作された、豊かな色彩でユニークなデザインを表現した白釉多彩陶器が目を引きました。卑近な例から言うと、昨年トルコに旅行しました。今回の展覧会の後半ですが、トルコの陶器の皿や鉢、瓶やタイルなど、数多く出ていたので嬉しくなりました。また「スルタン坐図」や真鍮製の「香炉」もありました。
なにしろ単にオリエントと言っても、幅が広くまた深いのが特徴です。農耕・牧畜がいち早く始まり、5000年以上も前に都市が存在しました。ユーラシア大陸とアフリカ大陸、地中海とインド洋を結ぶ地理的条件に多種多様な文化が行き交い、栄枯盛衰を繰り返しました。またユダヤ教やキリスト教、そしてイスラーム教など世界宗教の揺籃の地でもありました。世界四大文明のうち、エジプト文明とメソポタミア文明は中近東で誕生しました。ムン名誕生以前にも農耕・牧畜が始まって以降、様々な文化が培われていきました。
展覧会の構成は、以下の通りです。
第1章 文明の誕生―エジプト文明とメソポタミア文明
四大文明以前
古代エジプト
古代メソポタミア
第2章 ローマ時代の技術革新―ガラスの美
エトルリアの文化
不透明なガラス―コア・ガラス
吹きガラス技法の誕生とローマン・ガラス
シルクロードとササン・ガラス
第3章 実用の美―イスラーム美術
色彩のバラエティー・イスラーム美術
繊細な挿絵・ミニアチール
人々の嗜好品・イスラーム金属器
技術の再発見・イスラームガラス
第1章 文明の誕生―エジプト文明とメソポタミア文明
四大文明以前
古代エジプト
古代メソポタミア
第2章 ローマ時代の技術革新―ガラスの美
エトルリアの文化
不透明なガラス―コア・ガラス
吹きガラス技法の誕生とローマン・ガラス
シルクロードとササン・ガラス
第3章 実用の美―イスラーム美術
色彩のバラエティー・イスラーム美術
繊細な挿絵・ミニアチール
人々の嗜好品・イスラーム金属器
技術の再発見・イスラームガラス
「中近東文化センター改修記念 オリエントの美術」
出光美術館のオリエントコレクションは、エジプト・イラン・トルコ・地中海地域を中心に、多岐にわたる考美術品が充実し、国内有数のコレクションとなっています。出光佐三初代館長(1885~1981)は、オリエント美術の蒐集の経緯や目的などについて、多くを語っておらず、また記録もほとんど残っていません。しかし、そのはじまりは、1950年代終わり頃に、縁あってイランのルリスターン青銅器コレクションを入手する機会を得たことに端を発しています。後に出光美術館の理事となる三上次男博士(1907~87)がイスラーム陶器研究者でもあったことから、その監修の下にコレクションが充実し、1966年の開館時にはすでにコレクションの主要な一分野へと成長していました。そして1979年秋以降は中近東文化センター(東京三鷹市)で常時公開してきましたが、この度、陶器・金属器・ガラス器・石製品などから厳選したオリエント美術の名品展を、34年ぶりに出光美術館で開催いたします。今回の展覧会では、出光美術館のオリエント美術品の特徴である先史時代からイスラーム時代にわたる幅広い作品を紹介します。また種類も石製品・土器・陶器・ガラス器・金属器、そして細密画などバラエティーに富んだ作品を選びました。時代・材質・地域においてこれだけ多岐にわたる作品と点数を一コレクションで提供できるのは、日本では出光美術館のみでしょう。また日本では出光コレクションでなければ見られない作品や世界にも数例しかない作品も含まれています。世界の二大文明を含み、東西文化交流の交差点でもあった中近東の地で華やかに花開いた数々の作品を通して、オリエント美術の世界と中近東の歴史散歩をお楽しみください。
「出光美術館」ホームページ
 中近東文化センター改修記念
中近東文化センター改修記念
「オリエントの美術」
図録
平成25年1月11日発行
編集・発行:公益財団法人出光美術館
過去の関連記事:
出光美術館で「琳派芸術Ⅱ」(前期)を観た!
出光美術館で「東洋の白いやきもの―純なる世界」を観た!
出光美術館で「悠久の美」を観た!
出光美術館で「長谷川等伯と狩野派」展を観た!
出光美術館で「大雅・蕪村・玉堂・仙厓」展を観た!
出光美術館で「花鳥の美―珠玉の日本・東洋美術」展を観た!
出光美術館で「琳派芸術 第2部 転生する美の世界」展を観た!
出光美術館で「琳派芸術 第1部 煌めく金の世界」展を観た!
出光美術館で「茶陶への道 天目と呉州赤絵」展を観た!
出光美術館で「仙厓―禅とユーモア」展を観た!
出光美術館で「日本美術のヴィーナス」展を観た!
出光美術館で「麗しのうつわ―日本やきもの名品選―」展を観た!
出光美術館で「ユートピア 描かれし夢と楽園」展(前期)を観た!
出光美術館で「中国の陶俑―漢の加彩と唐三彩」展を観た!
出光美術館で「やまと絵の譜」展を観た!
出光美術館で「水墨画の輝き―雪舟・等泊から鉄齋まで」展を観た!
出光美術館で「小杉放菴と大観 響きあう技とこころ」展を観た!
出光美術館で「文字の力・書のチカラ―古典と現代の対話」展を観た!
出光美術館で「志野と織部」展を観る!
出光美術館で「国宝・風神雷神図屏風」展を観る!
「京都国立博物館」の建築
「近代建築史図集」(日本建築学会編彰国社刊)に片山東熊の作品は、「京都帝室博物館」1895年(明治28)、「表慶館」1908年(明治41)、「赤坂離宮」1909年(明治42)が載っています。1879年(明治12)、工部大学校造家学科からコンドルの教育を受けた日本人建築科4名が始めて世に出ました。辰野金吾・片山東熊・曽禰達蔵・佐竹七次郎の4名で、彼らは明治の建築界の元老として各方面で活躍します。
片山東熊は、工部大学校を卒業すると同時に工部省に勤め、師のコンドル設計の有栖川宮邸の建築掛を命ぜられます。これが彼の宮廷建築家としての生涯の開始になったのでした。各地の離宮・宮邸・華族邸・博物館・記念建物などの限られた範囲でしたが、彼は有能な部下たちと、皇室の権威のもとに動員できた絵画・彫刻・工芸などの芸術分野の大家をそろえて、華麗な建築をつぎつぎと建てました。
それらの作品は建物の性格上丁重に管理され、よく残されているものが多い。「奈良帝室博物館」1894年と「京都帝室博物館」1895年は、彼の中期の作風を示しています。ともに古都の環境を背景にしているだけに、そのルネサンス様式の純欧風は数々の批判を受けたというが、今日では十分にその環境に定着しています。上野の国立博物館の構内にある「表慶館」1908年も、やや重苦しいネオ・バロック様式の彼の作品ですが、彼の代表作は何といっても「赤坂離宮」1909年でしょう。(参考:「近代建築史概説」)
片山東熊の設計による「京都帝室博物館」については、ほとんど情報を持ち合わせていません。それはさておき、京都国立博物館、入口のチケット売り場やミュージアムショップからなる低く抑えられた建築は、どうみても谷口建築でしょう。奥で工事中の建築がありました。「平常展示館」です。掲示板には建築の竣工イメージ図と、その建築の概要が記されていました。やはり谷口建築設計事務所の名前が掲げられていました。新しい「平常展示館」のオープンは、平成26年春の予定だそうです。
「京都国立博物館」ゲート
「京都国立博物館」
「平常展示館」建替工事
過去の関連記事:
「国宝・迎賓館赤坂離宮本館」参観
国宝・旧東宮御所(現・迎賓館赤坂離宮)
東京国立博物館表慶館改修「よみがえった明治建築」
上野の「表慶館」、百年ぶり全面修復
土門拳記念館
東京国立博物館、グラビア撮影で人気





























































































































































































