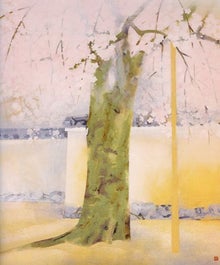山種美術館創立45周年記念特別展「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション」が、以下のように開催されています。
[前期]江戸絵画から近代日本画へ
2011年11月12日(土)~12月25日(日)
[後期]戦前から戦後へ
2012年1月3日(火)~2月5日(日)
「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション」展の後期、行ってきました。地下の展示室に入ると、今回だけはちょっと違います。「あれっ、なにこれ?」、油彩画がずらっと並んでいます。「日本画の専門美術館」を標榜する山種美術館ですが、いつもは日本画が掛かっているところに、今回はまずは「洋画」です。
最初に、小林古径の油彩画「静物」(1922)です。古径といえば「猫」(1946)もありますが、「清姫(全8面)」(1930)がよく知られています。紀州の道成寺の伝説、安珍・清姫の物語、なかでも空を飛ぶ清姫を描いた「日高川」が傑作です。たしか「前期」に出されていたと思います。がしかし、ここでは油彩画「静物」です。古径の唯一の油絵で、前田青邨との欧州留学直前に描かれた作品です。油彩画に落款が入っているところが日本画家・古径らしいと思います。
小出楢重の「子供立像」(1923)、ブリヂストン美術館に楢重の作品「横たわる裸身」(1930)や「帽子をかぶった自画像」(1924)がありますが、どれもこれも一工夫されています。この子供のモデルは5歳になる長男、左からさし込む光による陰影表現が特徴です。一度ちゃんと描いてから、それを変形させるのが楢重の作風です。子供も全体的にひねった感じで変形させています。その性格に肉薄して、しかもユーモアが漂っています。
和田英作の「黄衣の少女」(1931)、背景の赤い布と少女の黄色いワンピースが際立ったコントラストを生んでいます。少女のきりっと結んだ口元が、利発的で心の強そうな性格がよく表れています。梅原龍三郎の「バラと蜜柑」(1944)、全体的にルノワール風の雰囲気の静物画です。萬暦赤絵の壺に薔薇を生け、色彩豊かな林檎や蜜柑を添えています。
佐伯祐三の「レストラン《オ・レヴェイユ・マタン》」(1927)、レストラン名の文字と鶏が描かれた建物、なんとなく孤独で寂しげな佇まいです。佐伯は長年パリへいてその風景をたくさん描いたように思っていましたが、実はそうではなく、パリ到着後1年を待たずしてわずか30歳で亡くなります。荻須高德は渡仏後、佐伯祐三のもとで制作、画風にも佐伯の影響を多く受けています。昭和2年に東京美術学校卒業後渡仏、昭和61年、亡くなるまでパリで制作活動を続け、お墓もパリにあるという。作品は「食品店」(1962)です。
じつは、「ザ・ベスト・オブ 山種コレクション」展(前期)のブログに書いたものを、この項の画像を作成しているときに、誤って消してしまいました。今、修復中で、画像だけはなんとか戻したのですが、全部が全部、戻るかどうかはわかりません。ここで泣き言を言っても始まりませんが、そんなことがありちょっとショックでした。
「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション」展(後期)は、「近現代日本画」と「山種美術館と速水御舟」の項、できるだけ画像を多く載せようと思い、過去のブログに載せた過去の記事を参照したら、ほとんどの画像、だいたい95%位が今まで使われていたので、数枚新たにスキャンしただけで済みました。
山種美術館が九段にまだあったときに観たものが、すごく印象に残っています。奥村土牛の「醍醐」、「桜さくらサクラ・2009」 展でこの作品を最初に観ました。誰もが傑作だと認めている作品です。同じく土牛の「鳴門」も「雄大で神秘的な」渦潮を観た土牛は、夫人に帯を掴んでもらい、写生を何十枚もしたというから、その執念には頭が下がります。東山魁夷の「満ち来る潮」と、上村松篁の「白孔雀」は初めて観ました。ともに思っていた以上に大きな作品なので、画風はまったく異なりますが、驚きました。東山魁夷の「秋彩」(1986)と「年暮る」(1968)、ともに小さいながらも、傑作です。
高山辰雄の「座す人」(1972)、これも山種の系統とはちょっと異なる作品ですが、座して瞑想する人物を描いたもので、周辺の岩肌に溶け込むように描かれています。背後には一筋の滝が描かれ、清涼感と動きを与えています。深い精神性を感じます。今回の僕の一押しは、福田平八郎の「牡丹」(1924)です。満開の花が咲き誇る牡丹の木々を大ぶりに表した大作です。裏彩色を駆使して、花びらの繊細な質感や柔らかい色合いまで再現されています。「写実を追求することで、写実を超えた理想美をつくり上げている」といわれています。
山種美術館と言えば速水御舟、別室の展示室では御舟の作品がオンパレードです。重要文化財の「炎舞」(1925)の他、「百舌巣」(1925)、「紅梅・白梅」(1929)、「牡丹花(墨牡丹)」(1934)が出されていました。なかでも「牡丹花(墨牡丹)」は墨の濃淡だけで描いたもので傑作です。他に、金地屏風の大作「翠苔緑芝」(1928)も出されていました。
洋画
近現代日本画
山種美術館と速水御舟
「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション」展
1966(昭和41)年、日本初の日本画専門の美術館として誕生した山種美術館は、2011年で開館45周年を迎えます。これを記念し、当館が所蔵する約1800点の収蔵品の中から名品を選りすぐり、一堂に展示する特別展を開催いたします。当館のコレクションは、横山大観、上村松園、小林古径、加山又造、平山郁夫など、名だたる作家たちと直接交流を重ねる中で蒐集された日本画が核となっています。また、「幻の画家」と呼ばれた日本画家、速水御舟のコレクションは、質・量ともに国内外随一を誇ります。さらに、当館の収蔵品は日本画だけにとどまらず、琳派などの江戸絵画や浮世絵、近代の洋画も含まれています。今回の特別展では、岩佐又兵衛《官女観菊図》★、竹内栖鳳《班猫》★などの重要文化財や、切手になったことでも知られる村上華岳《裸婦図》★、福田平八郎《筍》☆、速水御舟《炎舞》[重要文化財]☆、奥村土牛《醍醐》☆をはじめ、当館の代表的な作品から隠れた優品まで約80点をセレクトし、前期と後期で全点を入れ替えてご紹介いたします。普段はまとまって展示されることのない傑作の数々が一堂に会する本展覧会を通じて、山種コレクションの真髄を心ゆくまでご堪能いただければ幸いです。
註:★前期展示(11/12~12/25)☆後期展示(1/3~2/5)
「ザ・ベスト・オブ・山種コレクション」
図録
監修:
山下裕二(山種美術館顧問・明治学院大学教授)
編集:
山種美術館学芸部
山崎妙子/高橋美奈子/三戸信恵/櫛淵豊子
発行:
山種美術館
過去の関連記事:
山下裕二の変化球「山種コレクションベスト10」!
山下裕二の「知られざる山種コレクション10選」を聞いた!
山種美術館で「ザ・ベスト・オブ 山種コレクション」(前期)を観た!(修復中)
山種美術館で「百花繚乱 桜・牡丹・菊・椿」展を観た!
山種美術館で「BOSTON 錦絵の黄金時代 清長、歌麿、写楽」展を観た!
山種美術館で「歴史画を描く―松園・靫彦・古径・青邨―」展を観た!
山種美術館で「日本美術院の画家たち―横山大観から平山郁夫まで」展を観た!
山種美術館で「日本画と洋画のはざまで」展を観た!
山種美術館で「江戸絵画への視線」展を観た!
山種美術館で「浮世絵入門」展を観た!
山種美術館で「生誕120年 奥村土牛」展を観た!
山種美術館で「大観と栖鳳―東西の日本画―」展を観た!
山種美術館で「速水御舟―日本画への挑戦―」展を観た!
山種美術館で「美人画の粋 上村松園」展を観た!
山種美術館で「桜さくらサクラ・2009」展を観た!
山種美術館で「松岡映丘とその一門」展を観た!
山種美術館で「大正から昭和へ」展を観た