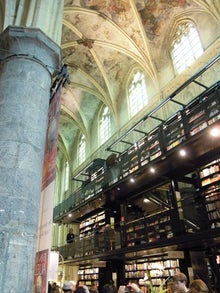ニューオータニ美術館で「マリー・ローランサンとその時代展」を観てきました。副題には「巴里に魅せられた画家たち」とあります。
ニューオータニ美術館にはもう何度か行きましたが、他にはない美術館の雰囲気とか特徴的な所蔵品で、好きな美術館の一つです。以前、勤務していた設計事務所がこの近くにあったのですが、その頃はサントリー美術館はありましたが、ニューオータニ美術館はまだこの場所での開館前だったと思います。絵画はだいたいなんでも観ますが、僕のちょっと苦手、というか、好きではない画家が何人かいます。マリー・ローランサンがその一人です。また東郷青児もその一人で、好きではありません。その二人の画家の展覧会があったとしたら、たぶん、観に行くことはないと思います。
さて、今回のニューオータニ美術館での展覧会は、「マリー・ローランサンとその時代展」です。結果として観てよかったと思います。一つは、マリー・ローランサンの若い頃の、いわば画家に成り立ての頃の作品が幾つか観られたこと、当然ですが、若い頃は普通の絵描いていたことが分かったのが、収穫と言えば収穫でした。それともう一つ、「その時代展」ですからローランサンと同時代の画家の作品が思っていた以上に数多く観られたことです。もちろん、以前にニューオータニ美術館で観た作品もありましたが、そうではない作品、初めて観る作品も数多く出されていました。
主催はもちろん「ニューオータニ美術館」ですが、なんと共催に4つの美術館の名前がありました。「マリー・ローランサン美術館」「高梁市成羽美術館」「一宮市三岸節子記念美術館」「神戸市立小磯良平記念美術館」の4館です。チラシの隅っこを見てみると、「全国美術館会議 小規模館研究部会 第2回共同企画」とありました。ネットで調べてみると以下のようにありました。
本展では、美術館の全国組織「全国美術館会議」加盟館の小規模館研究部会の第2回共同企画展として全国5か所を巡回しています。主催館ならびに協力館の所蔵作品のみで構成されており、小さな美術館の個性的なコレクションが、連携によってさらに輝きを増す様子も見どころといえるでしょう。
公立美術館だけに限ったやや規模の大きなものとしては、「美術館連絡協議会」という組織がありました。2009年に東京都美術館で「美連協25周年記念 日本の美術館名品展」を観たときに、そんな組織があることを初めて知りました。それとはまた違う組織のようです。いや、なかなかユニークな試みと言えるでしょう。ところがマリー・ローランサン美術館のホームページを見てみると、残念なことに「マリー・ローランサン美術館は2011年9月30日をもって閉館いたしました」とあったので、これまた驚きました。
展覧会の構成は以下の通りです。
第1章 パリの画家、マリー・ローランサン
第2章 パリの華やぎ
第3章 日本人画家の活動
今回展示された作品は、ざっと作品リストをみると、マリー・ローランサン美術館32点、ニューオータニ美術館11点、パナソニック汐留ミュージアム5点、兵庫県立芸術文化センター薄井憲二バレエコレクション11点、高梁市成羽美術館9点、神戸市立小磯記念美術館10点、一宮市三岸節子記念美術館6点、その他で構成されています。全部で112点、そうとうな作品数です。これでも分かる通り、ローランサンは別にして、ルオー、ヴァラドン、ヴァラマンク、ドンゲン、ドラン、ユトリロ、フジタ、キスリング、児島虎次郎、佐伯祐三、荻須高徳、小磯良平、三岸節子、等々、なかなか魅力的な作品が揃っていました。多くの画家を惹きつけてやまない「巴里の華やぎ」が伝わってくる展覧会でした。
第1章 パリの画家、マリー・ローランサン
第2章 パリの華やぎ
第3章 日本人画家の活動
「マリー・ローランサンとその時代展 巴里に魅せられた画家たち」
パリが生んだ画家マリー・ローランサンの活動を中心に、第一次世界大戦後の1910年代から30年代と、それに先立つ20世紀初頭のパリの美術動向にスポットをあてて、各国からパリに集った個性あふれる画家たちの姿を紹介します。多くの芸術運動が興った19世紀末から20世紀前半のパリで、華やかな色彩に愁いを秘めた女性像で知られるマリー・ローランサンが活躍しました。この時代のパリには、世界各地から芸術を志して様々な出自を持つ人が集まります。そこには日本から渡っていった多くの才能豊かな青年たちも加わりました。彼らは刺激を与え合いながら、パリという環境に個性を育まれて成長を遂げていったのです。
過去の関連記事:
ニューオータニ美術館で「ベルナール・ビュフェのまなざし フランスと日本」展を観た!
ニューオータニ美術館で「新春展」を観た!
ニューオータニ美術館で「日本画に見る四季の美展」を観た!
「造形作家友永詔三の世界 木彫りの乙女たち」展を観た!
ニューオータニ美術館で「安田靫彦展 花を愛でる心」を観た!
ニューオータニ美術館で「大谷コレクション展」を観た!